
学童の利用要件を満たしていないけれど帰宅時には親が家にいない、学童が満員で入れないなど、さまざまな理由で親のいない家に、自分で鍵を開けて帰宅する「鍵っ子」が増えています。
子どもを鍵っ子にするにあたって、不安を抱いているママやパパも多いのではないでしょうか。鍵っ子についてより詳しく知ることで対策を立てていきましょう。

鍵っ子デビューはいつから?
鍵を失くさないか、ひとりで留守番していられるかなど、心配は尽きない鍵っ子。何歳くらいで鍵っ子デビューする子が多いのでしょうか。
鍵っ子とは?
鍵っ子とは、学校からの帰宅時になんらかの事情で家族が自宅におらず、自分で鍵を開けて留守番する子どものことを指します。
いつも家の鍵を持ち歩いていることから「鍵っ子」と呼ばれ、一般的には小学生に対して使われることが多いです。
「鍵っ子」という言葉は、共働きが増加した1960年代頃から使われ始めました。
1998年には学童保育が法制化され、保護者の帰りを待つ時間を学童保育で過ごす子どもも増えています。
しかし、学童の利用条件を満たさない、学童が満員で入れない、子ども自身が学童に行きたがらないなど、さまざまな理由で鍵っ子となる子どももいます。
家庭の状況によってタイミングは異なる
鍵っ子になるタイミングは家庭の状況によって異なります。
祖父母と同居している、ママとパパどちらかが在宅勤務できるなどの家庭であれば、子どもの帰宅時に誰かが家にいる状況を作れるでしょうし、低学年で利用条件を満たしていれば、学童が利用できるでしょう。
鍵っ子になるタイミングとして多いのは、小学校1年生から4年生と言われています。
小学校に入ると幼稚園の延長保育や保育園よりも早い時間に下校することになるため、学童保育などの預け先がない場合には1年生から鍵っ子が選択肢にあがります。
また、学童保育を利用していた場合でも、中学年になると定員等の問題で学童が利用しづらくなったり、子ども自身が行きたがらなくなったりするため、鍵っ子になるケースが多いです。
いつから鍵を持たせるかは、子どもの成長具合や性格、家庭の状況と照らし合わせながら決めるのがよいでしょう。
鍵っ子に起こる問題やリスク
ここからは、鍵っ子に想定されるトラブルについて、具体的に見ていきましょう。
次からの章では、リスク対策もお伝えしますので、あわせて参考にしてください。
鍵を紛失してしまう
鍵の紛失は空き巣被害につながる恐れもあり、非常に危険です。
ランドセルにつけるタイプのキーケース、チェーン付のキーホルダーなどを活用し、落とさないようにしましょう。
家の鍵をスマートロックに付け替えるのもおすすめです。
親の留守を狙う不審者もいる
子どもだけで留守番している家庭は、不審者から狙われやすいです。
ドアチェーンをかける、不必要な電話や来訪者の応対はしないなどの対策をしましょう。
火災や負傷などの可能性がある
留守番中の子どもが自分で簡単な食事を用意しようとして包丁で怪我をしたり、火災を起こしてしまったり、やけどをしたり、といった事故が起こるかもしれません。
お腹が空いたときのルールについても親子で話し合いましょう。包丁や火を使わずに食べられるものを用意しておくのがおすすめです。
子どもに鍵を持たせるか判断するポイント
「そろそろうちの子にも鍵を持たせようかな」と考え始めたとき、何をもって判断基準とすればよいでしょうか。
ここでは目安となるポイントを3つご紹介します。
鍵の開け閉めがきちんとできる
まず、鍵の開け閉めがひとりできちんとできることは必須条件です。
それまで鍵を持っていなかった子どもは、鍵の取り扱いに慣れておらず、動きが硬くなってしまうことがあります。
まずは、スムーズに鍵を開け閉めできることがひとつの目安です。
家の中に入ったら必ず中から鍵をかける習慣もつけておきましょう。
一定時間、ひとりでお留守番ができる
鍵っ子は家族が帰ってくるまでひとりで留守番をするわけですから、一定時間ひとりで留守番ができそうかどうかも目安になるでしょう。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★子どものお留守番は何歳から?
緊急時に電話がかけられる
何かトラブルが起きたとき、すぐに電話をかけてママやパパに伝えることができるかどうかも目安のひとつになるでしょう。
スマートフォンや固定電話での電話のかけ方を教え、身についているか確認しましょう。
また、電話が鳴っても基本的にはでないようにするのが安心です。一方で、ママやパパといった信頼できる人からの電話にはでられるようにしておくと、なおよいでしょう。
鍵っ子の防犯対策で工夫できること
子どもに鍵を持たせる場合には、以下のような工夫でリスクが軽減できます。
鍵の大切さやリスクを伝える
まず、鍵は大切なものであり、慎重に管理しなくてはならないものだと子どもに伝えましょう。
鍵を失くしてしまったら家に入れないだけでなく、拾った人に悪用されるかもしれません。
また、家に入れずにいる間にトラブルに巻き込まれるおそれもあります。
鍵を失くすとどのように困るのか具体的に伝え、鍵は友だちに見せびらかしたり、遊び道具に使ったりするものではないときちんと理解させることが大切です。
キッズケータイやGPSを持たせる
GPS機能つきのキッズケータイや、GPS端末を持たせるのも有効です。
キッズケータイは通話もできて便利ですが、持ち込みを禁止している学校もあります。そのような場合には、GPS機能のみの端末をランドセルに入れておくとよいでしょう。
大きな声で「ただいま」という
子どもが自分で鍵を開けて、無言で家に入っていく姿を見られると、「家に誰もいないのかな?」と思われがちです。
誰もいないとわかっているときでも、大きな声で「ただいま」という習慣をつけておきましょう。子どもをトラブルから守るには、親が不在であると気づかれないことが有効です。
ご近所さんと良好な関係を築く
子どもを見守る大人の目は多ければ多いほど、トラブルを防げるもの。
積極的に挨拶し、近所の人と良好な関係を築いておきましょう。
ルール決めや防犯対策をしっかり行いましょう!
鍵っ子デビューは子どもも親も心配なもの。
しかし、いつかは鍵を持ち歩くようになります。ただやみくもに不安がるのではなく、鍵の取り扱いに関するルールを決める、安全を守るための防犯対策を取るなどして、不安を解消していきましょう。
ドキドキしながら帰った先には、いつの間にか成長したわが子が待っているかもしれません。
ライター:サカイケイコ
3児の母。おかあさんだからって好きを諦めない、をモットーに、仕事に家事に育児に趣味に全力投球中。
SNSで見かけて面白そうだなと思っていた「100の目標」を立ててみました。さて、いくつ実現できるかな…!
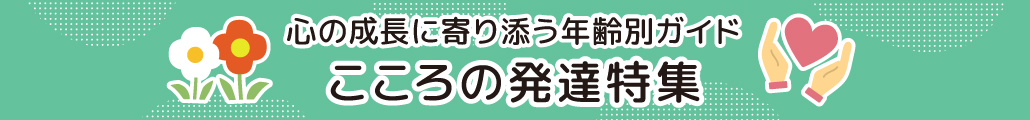

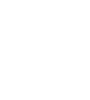


















 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す