
近年、登校しぶりは増加傾向にあり、パステル総研の調査によれば76.7%の保護者が登校しぶりで悩んだ経験があると答えています。
この記事では、登校しぶりとはどのようなものか、子どもが見せる登校しぶりの前兆、登校しぶりになる原因、親が取るべき対処についてお伝えします。

学校へ行くのをしぶる状態のこと
登校しぶりとは、学校へ行きたがらないことです。何かと理由をつけて欠席しようとしたり、登校準備に時間がかかったりします。
不登校との違いは?
不登校について、文部科学省は「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義しています。
登校しぶりは、不登校ほどではないものの登校することに対して不安やストレスを感じている状態です。一過性のこともあれば、長期化することもあります。登校しぶりから不登校に発展する可能性もあり、適切な対応やサポートが求められます。
登校しぶりの前兆
登校しぶりの前兆にはさまざまなものがあります。ここでは、登校しぶりをする子どもに比較的多く見られるサインを4つご紹介します。
体調不良を訴える
よく見られるのが腹痛や頭痛などの体調不良を訴えるケースです。朝、登校時間が近づくにつれて腹痛や頭痛に見舞われますが、登校時間を過ぎ日中になると元気になることも多いです。
登校のストレスから本当に調子を崩している場合もありますし、中にはどうしても学校に行きたくなくて仮病を使うケースもあります。
朝起きられない、準備が遅い
学校に気持ちが向かないために、朝起きられなかったり登校のための準備が進まなかったりします。
中には、起立性調節障害の影響で朝起きられないケースもあります。起立性調節障害は自律神経の失調により脳への血流が低下する病気で、午前中に倦怠感や起床困難などの不調を起こすことが多いです。あまりにも朝起きられないことが続くようであれば、一度受診してもよいでしょう。
学校生活での話題を避ける
学校生活について聞いても答えなかったり話を逸らしたりという行動が見られるようであれば、学校生活にストレスを感じているのかもしれません。
とはいえ、元々あまり学校のことを話さない子どももいますし、学年が上がるにつれて親には話したくないことも増えてきます。
「行きたくない」と言葉にする
はっきりと「行きたくない」と言う場合もあります。
学校へ行きたくないという気持ちを言えない子どもが多い中で、「行きたくない」と意思を口にするのは、保護者との信頼関係がしっかりできているからなのかもしれませんし、行きたくない気持ちが相当強いのかもしれません。
「行きたくない」という言葉を軽くあしらわず、真摯に受け止めましょう。
登校しぶりのきっかけや原因は?
登校しぶりは、環境の大きな変化や人間関係のトラブルが原因となることが多いとされます。具体的にどんなものが考えられるのでしょうか。
入学間もない小学1年生の時期
環境の大きな変化として小学校への入学があります。幼稚園・保育園とは環境も生活パターンも大きく異なり、戸惑う子どもは少なくありません。
入学だけでなく、進級も登校しぶりの原因となりやすいです。この時期は子どもの様子に特に注意しましょう。
長期休み明け
夏休みや冬休みといった長期休み明けも登校しぶりが起きやすいです。理由としては、「前学期に感じていた負担やストレスを思い出すから」「長期休業中に崩れてしまった生活リズムが元に戻せないから」などさまざまですが、学校生活をプレッシャーに感じていることは共通しています。
学校生活でのストレスやトラブル
学校生活のストレスやトラブルが原因で、「学校に行きたくない」と感じ、登校しぶりに繋がることがあります。
原因となるストレスやトラブルをはっきり認識している場合もあれば、なんとなく「学校に行きたくない」と感じている場合もあります。しかし、原因が解決すればすんなり登校するようになるケースも多いです。
成績の不安やプレッシャー
学年が上がると増えてくるのが、成績の不安から学校に行きたくないと感じるケースです。
「授業の内容がわからない」「テストの結果が思わしくない」といった学習面の悩みが大きくなると、子どもは学校生活に対して自信を持てなくなり登校しぶりに繋がります。
登校しぶりが見られたときの向き合い方
子どもに登校しぶりが見られたとき、ママやパパはどのように対処すればよいでしょうか。ここでは5つのポイントをご紹介します。
①無理やり行かせようとしない
まずは、無理やり学校に行かせようとしないことです。欠席が続くと授業についていけなくなるのではないか、友人関係に問題が生じるのではないかと不安に感じるママやパパも多いでしょう。
しかし、ママやパパの不安な気持ちや、無理に学校に行かせようとする行動がさらに子どものプレッシャーに繋がり、さらなる登校しぶりに繋がってしまう恐れがあります。また、「ママやパパはわかってくれない」と親に対する不信感が生まれ、状況が悪化するかもしれません。
②子どもの気持ちに寄り添う
「今日は学校に行きたくないんだね」と子どもの気持ちを受け止め、その気持ちに寄り添いましょう。
子どもと話している中で、「そんなつまらないことで学校を休むなんて」「それくらい我慢できなくてはこの先やっていけない」と感じることもあるでしょう。しかし、子どもにとって学校生活は大きなウェイトを占めるもの。そのため、大人からすればちょっとした思い込みに過ぎないことが原因で学校が嫌になることもあります。
「パパも仕事に行きたくないときがあるけどね、行ってみると面白いこともあるんだよ」などと子どもが「行ってみようかな」と思えるような声がけをしてみましょう。
③会話から登校しぶりの理由を探す
何気ない会話の中から、登校しぶりの理由を探してみましょう。
日常の会話の中で、「○○ちゃんは言葉がきついから嫌だ」などの発言があれば、それが登校しぶりの原因かもしれません。追求することはせず、小さなサインを集めていきましょう。
④生活習慣を見直す
習い事で帰宅時間が遅かったり、ゲームを夜遅くまでやっていたりして、知らず知らずのうちに生活が夜型になり、朝起きるのがつらくなっている場合もあります。
子どものタイプや家庭環境によって最適な生活パターンはさまざまです。日々の生活に無理がないか、生活習慣を見直すことも大切です。
⑤学校と連携する
登校しぶりが頻繁に見られるようなら、学校に相談し先生と連携することも考えてみましょう。
文部科学省の学校保健統計調査(令和5年度)によれば、9割以上の小学校でスクールカウンセラーが配置されています。相談相手としてスクールカウンセラーを活用するのもひとつの方法です。心理学の専門家の立場から、子どもが学校生活を安心して送れるようサポートしてくれるはずです。
子どもの気持ちに寄り添いましょう!
登校しぶりとはどのようなものかご紹介しました。
登校しぶりは、子ども自身の戦いでもありますが、親の「行かせなくては」という気持ちとの戦いでもあるのかもしれません。
大事なのは、子どもの気持ちに寄り添うこと。無理に登校を促すのではなく、子どもの「行きたくない」に寄り添いつつ、特別視せず普段通りの生活を送りましょう。
ライター:サカイケイコ
3児の母。おかあさんだからって好きを諦めない、をモットーに、仕事に家事に育児に趣味に全力投球中。
SNSで見かけて面白そうだなと思っていた「100の目標」を立ててみました。さて、いくつ実現できるかな…!
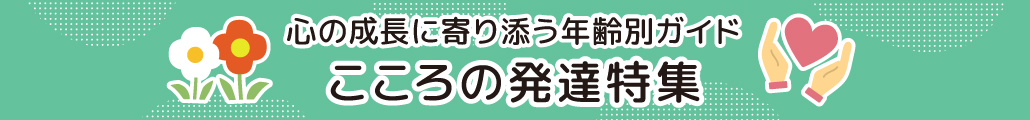

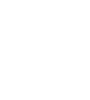










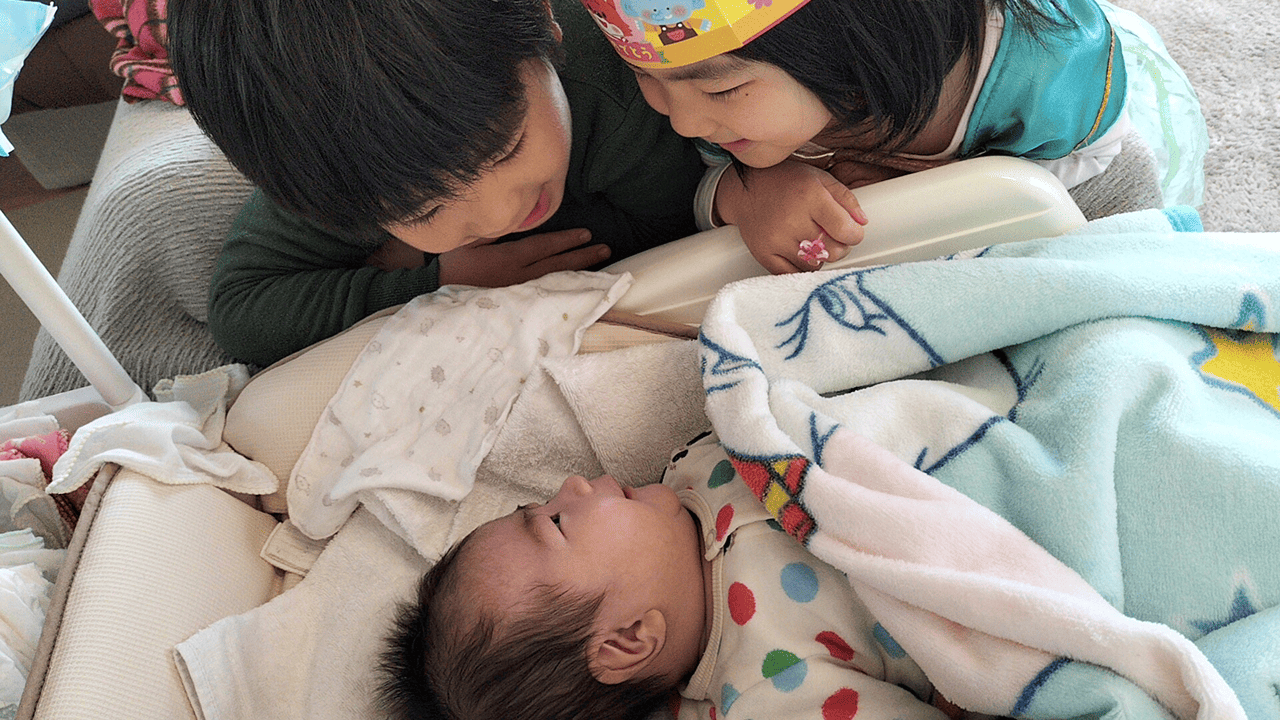



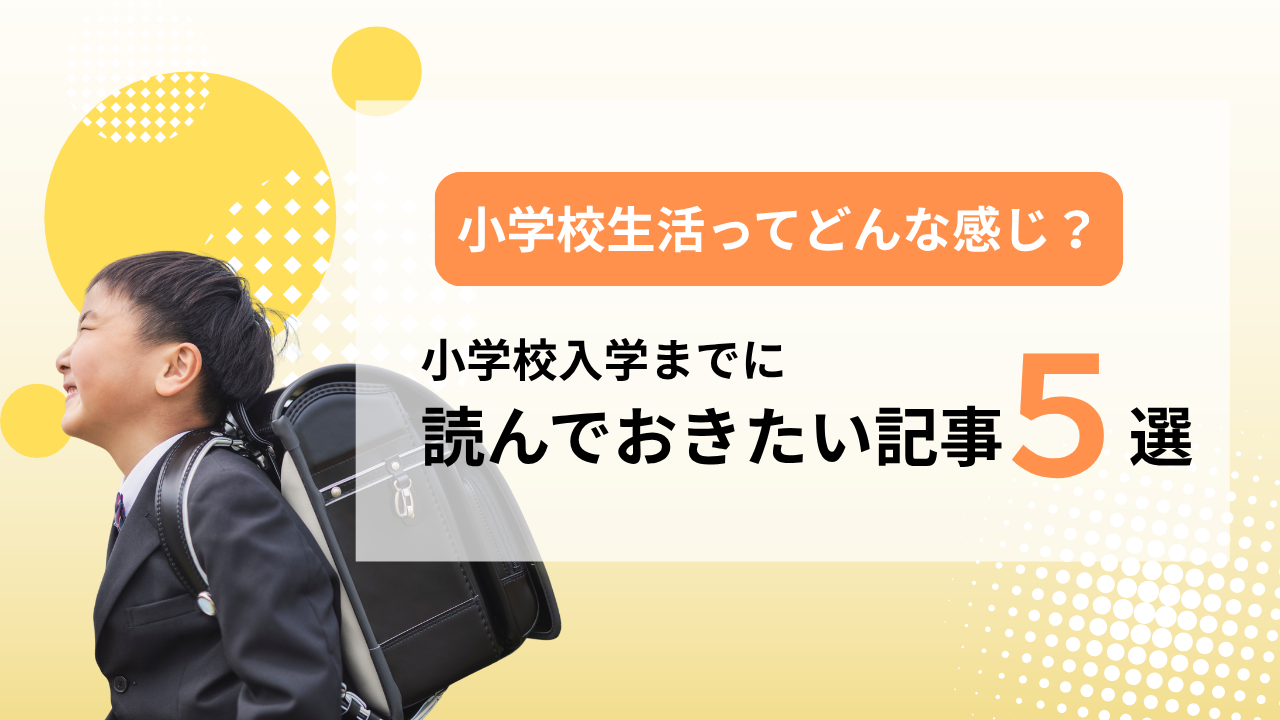








 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す