
乳児期は首が据わったり寝返りをうてるようになったり、日々目覚ましい成長が見られます。初めて子育てをしているママやパパは、いつからハイハイができるようになるのか気になったり待ち遠しく感じたりするでしょう。今回の記事では、けいこ豊洲こどもクリニック院長の塚田佳子さん監修のもと、赤ちゃんがハイハイを始める時期の目安や練習する方法などについて解説します。成長や発達には個人差がありますので、参考としてお読みください。

この記事を監修いただいたのは…
けいこ豊洲こどもクリニック院長:塚田佳子さん

小児科専門医、子どもの心相談医。けいこ豊洲こどもクリニック院長。
獨協医科大学医学部卒業。同大附属病院勤務等を経て2020年から現職。
2023年にはパークタワー勝どき小児科を開院。
2人の小学生男児の母として、日々、ママ目線で診察中。
ハイハイが始まる時期はいつから?
ハイハイとは四つ這いで両手と両膝をつき、手足を交互に出しながら進む動きですが、やり方はさまざまです。お座りから歩行までの間にできるようになる子が多くいますが、子どもの成長や発達には個人差があるため早い時期からできる子もいれば遅い子もいます。
ハイハイを始める目安は生後8か月頃
厚生労働省の「令和5年 乳幼児身体発育調査(調査結果の概要 p15)」によると、一般的にハイハイを始める時期は生後8か月頃です。早い子は6か月頃から始まり、約半数の赤ちゃんが7~8か月頃にはハイハイができるようになると言われています。9~10か月頃には約9割の赤ちゃんがハイハイで移動できるようになり、1歳前にハイハイできるようになる赤ちゃんがほとんどです。
ハイハイが始まるまでの発達の流れ
ハイハイはある日突然できるようになるわけではなく、いくつかの成長や発達の段階を経てできるようになっていきます。発達の流れを理解することで、わが子がハイハイできるようになる兆候を感じ、適切な援助をすることが可能です。
発達①|寝返りをする
一般的に赤ちゃんは生後3~4か月頃に首が据わってうつ伏せができるようになり、生後5~7か月頃には寝返りがうてるようになります。ハイハイはうつ伏せの姿勢で行うため、寝返りがうてるようになって、自分でうつ伏せの姿勢を取れることが第一歩です。
発達②|おすわりをする
寝返りがうてるようになり、うつ伏せの姿勢にも慣れておすわりができるようになるのが次の段階です。最初は不安定ですが、徐々に体のバランスが取れるようになり、1人で安定して座れるようになります。腰や下半身が発達し、おすわりがしっかりできるようになることが次のステップです。
発達③|ずりばいをする
ずりばいとは、お腹を床につけた状態で腕や足を使って移動する動作です。腰が据わる前やハイハイに必要な筋力が十分でない時期でも始まる動きで、ハイハイに必要な筋肉が未発達でも自力で移動できるようになります。ずりばいに慣れていないうちは、後退したり同じ場所でグルグル回ったりすることもあります。
発達④|ハイハイをする
ずりばいで移動できるようになった後、ハイハイに移行する子が多くいます。しかし、ずりばいをせずにハイハイを始める子もいれば、ハイハイをほとんどせずに次のつかまり立ちや歩行に移行する子もいるなど子どもによってさまざま。「ずりばいをしない」「ハイハイをしない」などと心配せず見守りましょう。ずりばいの時期に四つ這いの姿勢で体を前後に動かす様子が見られたら、ハイハイに移行するサインです。
以上4つの発達の流れは個人差があり、子どもによって順序が変わったり、やらないものがあったりするので気長に様子を見守ることが大切です。
ハイハイの練習方法
ハイハイをすることで、手足で体を支える経験を積んで筋力が発達します。じっとしていることが多かったそれまでに比べて運動量も大幅に増え、股関節が発達していくなどハイハイには大きな効果があるため、練習をするのもよいでしょう。ハイハイをするための、3つの練習方法を解説します。
ただし、ハイハイの時期や期間には個人差があるため、時期が遅いとか期間が短いなどと心配する必要はあまりありません。遊びの中で楽しく取り入れてみてください。
うつ伏せの時間を少しずつ長くする
ハイハイをするには、うつ伏せから四つ這いの姿勢を取ることが必要です。赤ちゃんをうつ伏せにさせると、徐々に手をついて体を支えたり前後に移動したりするずりばいの動きにつながり、ハイハイへも移行しやすくなります。
おもちゃなどを使い、前に進みたいと思える環境をつくる
興味を惹くものが視界に入ると、そこまで進んでよく見たりさわったりしようとします。あえて少し離れたところにおもちゃなど安全で赤ちゃんの好きなものを置いておくことも効果的です。
足の裏を押すなど、進むためのサポートをする
うつ伏せになっても前進する様子が見られなければ、進みやすいように足の裏を押してあげましょう。無理やり進ませようとするのではなく、前進するためのサポートをする気持ちで優しく押すことがポイントです。
ハイハイをし始めたら気をつけること
ハイハイをするようになると行動範囲が大きく広がるため、危険も高まります。赤ちゃんの安全を守るために注意すべきポイントは、次の3つです。
こまめに掃除をし、床を清潔に保つ
床に手足をつけて移動するハイハイの時期はいつも以上にこまめに掃除を行い、床を清潔に保つことが大切です。床に落ちている埃やゴミを口に入れたり、床についた手でつかんだものを口に入れたりすることもあるため、常に清潔な環境を心がけましょう。
手が届く場所に物を置かない
舐めても問題ないものならよいですが、誤飲の危険性も高まるため赤ちゃんが口に入れて危険なものはあらかじめ取り除きましょう。床だけではなく、ローテーブルなど赤ちゃんの手が届く高さの場所にも物を置かないよう注意が必要です。また、できるだけのびのびと動き回れるよう、可能な範囲で広い環境を整えましょう。
大人の目が届く範囲で遊ばせる
四六時中赤ちゃんから目を離さずにいることは難しいですが、できるだけそばを離れず何かあったときにすぐに対応できるように心がけることも重要なポイントです。トイレやキッチン、風呂場など別の部屋に行くときはドアを開けておく、ハイチェアやバウンサーなどを活用して一緒に部屋を移動する、できるだけ寝ている時間に用事をすますなどの配慮を心がけましょう。
赤ちゃんの発達には個人差がある
今回は赤ちゃんのハイハイについて詳しく解説しました。ご紹介したとおり、赤ちゃんの成長や発達には個人差があります。ほかの子の様子を見聞きする機会があると、わが子と比較して心配してしまうこともあるでしょう。しかし、心配しすぎず成長した様子に目を向けて、温かく適切なサポートを心がけましょう。
文:西須洋文
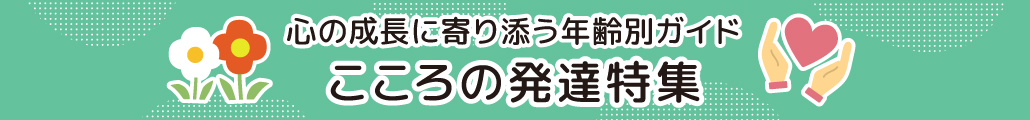

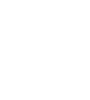























 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す