
「発酵食品が体にいい!」とよく聞きますね。味噌やヨーグルト、納豆などは発酵食品の中でも食卓にのぼることが多いのではないでしょうか。
しかし、発酵食品はなぜ体にいいといわれているのかご存じですか?
その理由や子どもへの効率的な食べさせ方をご紹介します。

発酵食品ってなに?
そもそも、発酵食品とはどのように作られているのでしょうか? また、発酵食品にはどんなものがあるのか確認しましょう。
発酵食品にはどんなものがあるの?
和食で多く使用される発酵食品に「納豆」「醤油」「味噌」「かつおぶし」があります。ヨーロッパでは「チーズ」や「ヨーグルト」「パン」「ウスターソース」が発酵食品として有名です。
意外なところでは「紅茶」も発酵を利用して作られています。
健康にいいってホント?
自然界に生息する微生物が炭水化物やたんぱく質などを食べてエネルギーをとり出す時、「エタノール」や「酢酸」などを生み出しています。
この生み出された物質が私たちにとってプラスになるものを「発酵」、マイナスになるものを「腐敗」と呼びます。
つまり、「発酵」は体にとってプラスになるものです。
微生物は食品を発酵させる過程で、栄養素を分解していきます。
私たちの体は、胃や腸で食べものを消化・吸収して栄養をとり込みますが、微生物が先に栄養素を分解してくれるため、消化・吸収しやすくなる利点があるのです。
また、この発酵の過程で炭水化物やたんぱく質が分解されると、健康にいいといわれる成分を生み出すことがあります。
納豆の糸(ネバネバ成分)の一種であるγ-ポリグルタミン酸は、血糖値の上昇を抑制するといわれています。
また、酢酸菌がアルコールを発酵して作る酢酸は、便秘改善に働くといわれています。
「プロバイオティクス」と「プレバイオティクス」
腸内細菌のバランスを保つなど、健康に対して有益な微生物を「プロバイオティクス」といいます。最近ではヨーグルトのパッケージに表記されていることもありますね。
発酵食品ではヨーグルトの他、納豆や漬物、醤油や味噌など、乳酸菌やビフィズス菌を含むものがプロバイオティクスに当てはまります。
これらの菌は腸で働きますが、ずっと腸内に住み続けてくれるわけではありません。そのため毎日少しずつでも食品からとり入れ、補給していく必要があります。
似たような名前ですが、「プレバイオティクス」というものがあります。プレバイオティクスは、腸内で有益といわれる菌を増やしたり、大腸の腸内細菌叢(フローラ)を健康的に改善する働きがあります。野菜や果物、豆類に多く含まれている「食物繊維」や「オリゴ糖」が当てはまります。食物繊維やオリゴ糖は腸内の菌のエサとなり、善玉菌を増やす一助になります。
善玉菌が増えると、腸内環境の悪化による便秘や下痢のリスクを低下させたり、体の免疫機能を高めるなどうれしいメリットが。
また、免疫機能が高まることで病気などのストレスに強い体を作ったり、病気の発症予防なども期待できます。「プロバイオティクス」を含む発酵食品を毎日とり入れつつ、「プレバイオティクス」で善玉菌を増やしていくことが大切です。
子どもにも同じ働きが期待できる?
発酵食品は、子どもにも同じように働くのか気になりますよね。大丈夫、子どもにも発酵食品は有用です。
3歳までの環境で腸内細菌が決まる
赤ちゃんはお腹にいる時、腸内細菌はいないといわれています。生まれる時に母親の産道で口から菌が入り込んだり、大人と一緒にお風呂に入ったりすることで伝搬するといわれています。
また、その後の生活によって個人特有の腸内細菌が定まり、食事内容が大人と同じようになってくるおよそ3歳までに腸内細菌の種類が決まってくるといわれています。
3歳までの子どもにどうやって食べさせると栄養がとれる?
3歳までの子どもは、胃腸がまだまだ未発達だったり、奥歯が生えていなかったりしてどのように発酵食品をとったらいいのか迷うかもしれませんね。
ヨーグルトは離乳食中期(7~8か月)から食べられます。多くのヨーグルトに含まれる乳酸菌は、60℃以上に加熱すると死滅してしまいます。
しかしヨーグルトは離乳食期でも加熱することなく使用できる食材です。甘味料の少ないベビー用のヨーグルトを使用しましょう。
また、醤油・味噌も離乳食中期(7~8か月)から使用できます。ただし塩分が多いので、1食0.5g程度を風味づけに使いましょう。味噌汁として飲めるのは離乳食後期(9~11か月)ごろからです。
3歳でも子どもの1日の食塩摂取量の目安は4g程度なので、大人のものよりも薄めてあげてくださいね。
納豆も離乳食中期(7~8か月)ごろから食べられます。普通の納豆では粒が大きいので、ひきわり納豆がオススメ。普通の納豆を刻んでもOKです。食べにくい場合は野菜と一緒に炒めても食べやすくなります。
しかし納豆の中の「ナットウキナーゼ」は熱に弱く、離乳食期には湯通しなど加熱して与えることが多いので、ナットウキナーゼは摂取しにくくなります。
ナットウキナーゼなどの酵素以外の栄養素は加熱しても壊れないので、安心してくださいね。
子どもが3歳以上でも腸内環境は整えられる
「腸内細菌の種類は3歳までの環境で決まってくる」とお伝えしましたが、もちろん3歳以上になっても腸内環境は整えられます。
3歳になると、奥歯が生えて固いものも食べられるようになってくるので、漬物やチーズ、加熱をしないそのままの納豆などの発酵食品もとり入れられます。
また、食物繊維やオリゴ糖がたっぷりの大豆やゴボウも食べられるようになりますね。
乳酸菌やビフィズス菌などを含む発酵食品(プロバイオティクス)を毎日少しずつ食べながら、善玉菌のエサになる食物繊維やオリゴ糖を含む食材(プレバイオティクス)をとり入れていきましょう。
逆に、たんぱく質や脂質が多く含まれる食事を中心にとっていると悪玉菌は増えていきます。
不規則な生活も悪玉菌を増やす一因となるので、可能な範囲で正していけるといいですね。
一緒に楽しめる味噌作り
発酵食品の中でも、手軽に作れるのが「味噌」。ステイホームで自宅にいることが多い今だからこそ、お子さんと一緒にご自宅で味噌を作ってみませんか?
子どもに味噌作りがオススメな理由
味噌は「大豆」「米麴」「食塩」の3つの材料があれば、簡単に作ることができます。
味噌はたいていの場合、
①大豆を水で戻す
②大豆を煮る
③煮た大豆をつぶす
④食塩と米麹を混ぜておく
⑤つぶした大豆と④を混ぜる
⑥団子状にする
⑦容器に入れる
⑧寝かせる(発酵させる)
の順で作られます。
大豆を煮る工程は火を使うので大人の方が行いましょう。それ以外の工程は包丁も火も使わないので、手を切ったり、やけどをする心配はありません。
※あたたかい大豆をつぶす時だけ気を付けてくださいね。
つぶした後の大豆は粘土のような触り心地なので、子どもにもなじみがあります。柔らかいので小さなお子さんでも一緒に作業ができますよ。
そのため味噌作りは子どもにオススメです。お団子状にする工程は、もしかしたらお子さんの方が上手かもしれませんね。
味噌としてすぐに食べられるようにはなりませんが、できあがりを毎日楽しみに待っていきましょう。
食育にもつながる
自分で作った味噌を食べることは、食育にもつながります。
家族や友人と一緒に味噌を作ったり、食べたりすることで食事の楽しさ、大切さを学べますね。
また、味噌は日本人の生活にかかせない伝統的な調味料です。味噌作りを通して、なじみのある食品がどんな材料からどういった過程を経て、見たことのある形へ変化するのかを知ることは、食への関心や意欲につながります。
作った味噌で味噌汁作りにも挑戦してみると、より食に対する興味が深まるのではないでしょうか。
自分の作った味噌汁であれば、苦手なものが入っていても挑戦してみよう! という気持ちになります。
キッズアライズのまとめ
発酵食品は、微生物が炭水化物やたんぱく質などを分解して生み出された物質によって作られます。
POINT
- 発酵は私たちのプラスになるもの。
- 「プロバイオティクス」を含む発酵食品を毎日とり入れつつ、「プレバイオティクス」で善玉菌を増やしていくことが大切。
- 3歳までの子どもはヨーグルトや納豆を使用。味噌や醤油などの調味料は風味づけ程度に。
- 3歳以上でも毎日少しずつ食品を食べていくとよい。
- 味噌作りは大豆を煮る作業以外は包丁や火を使わないので子どもでも安心。
色々な発酵食品があるので、子どもが食べられる食材でとり入れていけるといいですね。毎日の食事に発酵食品を少しずつとり入れ、腸の中の善玉菌を増やしていきましょう。
また、味噌などの発酵食品を作ることで、食への関心や意欲がわいてくることもあります。
お子さんと一緒に挑戦してみるのもオススメです。
[管理栄養士・ライター:おおすかさとみ]
食べることが大好きな2児のママライターです。以前は病院で栄養指導などの栄養管理を行っていました。
特定保健指導も経験しながら、栄養・食事についてわかりやすく伝えていきます。
キッズアライズ編集部からのお知らせ
キッズアライズ公式YouTubeにて料理家・蓮池陽子先生を講師に迎え、味噌づくりを実際にやってみました!
詳しくはこちらの記事をご覧ください!
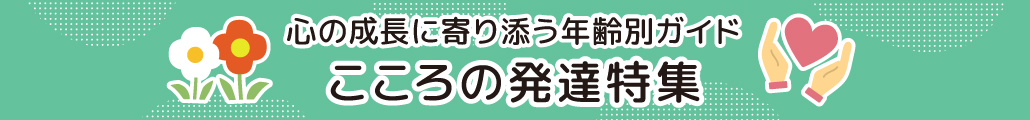

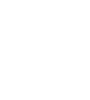






















 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す