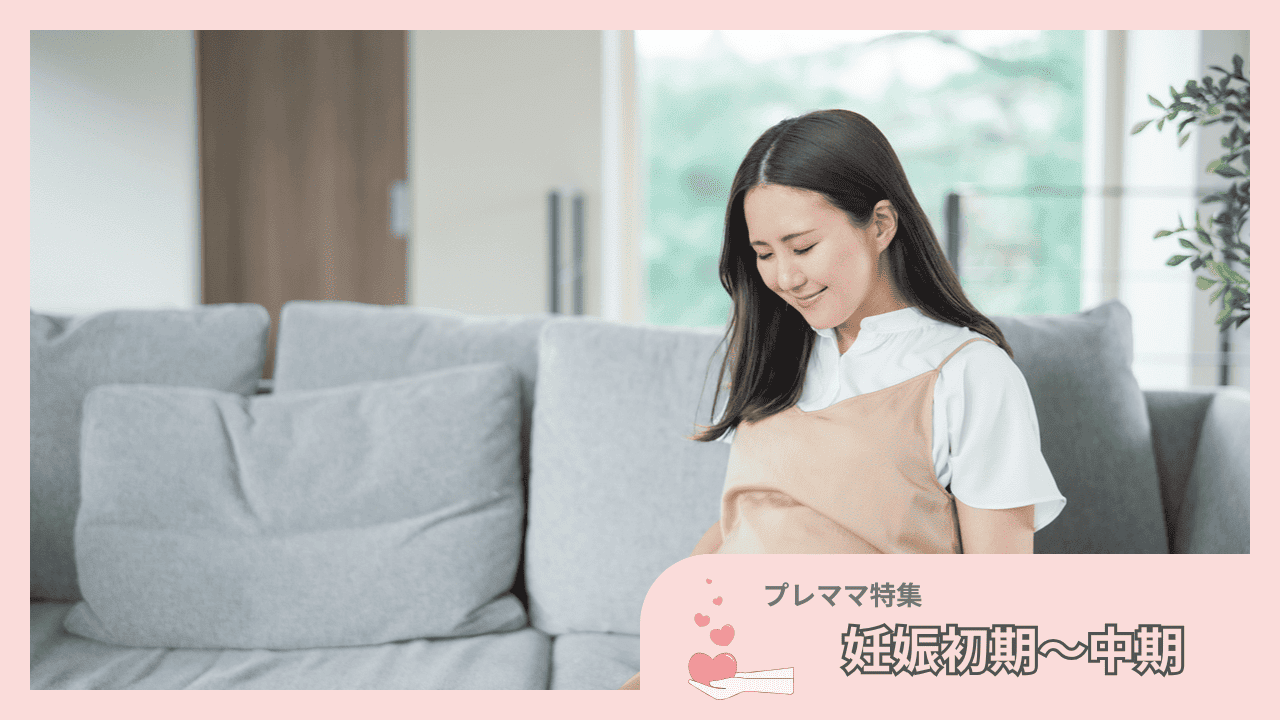
ママの体内ですくすく育つ赤ちゃん。ママは安定期に入るころから、赤ちゃんの動きにともない胎動を感じられるようになります。
ママにとって赤ちゃんの存在を感じる胎動は待ち遠しいかもしれません。
この記事では、八丁堀さとうクリニック副院長の佐藤杏月さん監修のもと、胎動はいつから始まるのか、感じ方や体内の赤ちゃんの様子などを詳しく紹介します。

この記事を監修いただいたのは…
八丁堀さとうクリニック副院長・産婦人科医:佐藤杏月さん

日本医科大学卒。日本医科大学武蔵小杉病院を中心に16年間産婦人科医として地域のハイリスク妊婦や、婦人科疾患の診療を行ってきた。
3人の子どもの子育てと仕事の両立を目指し、整形外科医の夫とともに2020年八丁堀さとうクリニックを開業。
医療法人社団双葵会八丁堀さとうクリニック副院長、医学博士、日本産婦人科学会専門医。
どんな胎動?妊娠時期別の感じ方の違い
子宮の壁を通じて、ママに伝わるおなかの中の赤ちゃんの動きを胎動といいます。
「安定期に入ってから」「妊娠後期になってから」など胎動に気づく時期や、その感じ方は人によって幅があるのが特徴です。
妊娠初期(~妊娠4か月)の胎動
妊娠初期は、超音波検査で赤ちゃんの心臓の音や動いている様子を確認できますが、胎動がわかるほどではありません。まだ赤ちゃんはとても小さく、その動きが子宮の壁からママに伝わりにくいからです。
妊娠中期(妊娠5~7か月)の胎動
妊娠中期はママのおなかが少しずつ目立ちはじめるころ。赤ちゃんも初期より大きくなって、活発に動くようになります。この時期になると、赤ちゃんが動くと胎動として伝わりやすいでしょう。
赤ちゃんのポコポコとした蹴りや押されるような感覚もわかって、おなかの中の存在を実感しやすくなります。
妊娠後期(妊娠8~9か月)の胎動
妊娠後期には赤ちゃんもさらに成長します。子宮内の限られたスペースの中でも、手や足を使った伸びの動きや子宮の壁を押す感じの胎動が増えていきます。
おなかが力強く押される感覚やグニュグニュと動く感覚などが確認できるでしょう。
臨月の胎動
臨月に入るといよいよ出産が近づき、赤ちゃんは頭を下に向けて骨盤の中へと入る体勢に変わっていきます。
赤ちゃんの動きが制限されるため、以前よりも胎動をあまり感じなくなったと思う人もいるでしょう。この時期には、子宮が突き出すような強い胎動も見られます。
胎動カウントで成長を確かめよう
赤ちゃんが元気に活動しているか、胎動で確認する方法もあります。
なかでも「10回胎動カウント法」は、ママが自宅で手軽に行いやすいおすすめの方法です。
手順は以下のとおりです。
- 妊娠28週を過ぎてから実施する
- 楽な姿勢になって最初に確認できた胎動を1回とし、順次カウントしていく
- 10回になるまでにかかった時間をはかる
目安として20分くらいの間に10回の胎動をカウントできれば、正常範囲と考えてよいでしょう。
胎動がきちんとあれば、おなかの赤ちゃんが元気に育っている証拠。
毎日、胎動を意識することで、妊娠中の不安を軽減できるかもしれません。
胎動がいつもより極端に弱かったり少なかったりする場合は、かかりつけの医師に相談しましょう。
胎動を感じやすい人の特徴
胎動の感じやすさには個人差があります。実際にどのような人が気づきやすいのでしょうか。
経産婦
出産経験のある女性は、前回の妊娠時に胎動を経験しているため、早い時期に気づくケースが多いようです。経産婦は、それまでの出産でおなかの筋肉や子宮がやわらかくなって伸び縮みしやすいため、胎動をより感じやすい面もあるでしょう。
また、胎動を感じやすい条件に、ママが心身ともにリラックス状態にあることが挙げられます。経産婦は妊娠や出産の経過をイメージできるため、心理的にもゆとりが生まれやすいのも影響しているかもしれません。
瘦せ型の体型
痩せ型の妊婦は脂肪がある妊婦よりも胎動を認識しやすく、また皮下脂肪が少ないため、見た目にもわかるくらい、おなかの形も変化しやすくなります。
赤ちゃんが動いた際に、手や足の形が表面に浮き出るなど胎動を視覚的に確認できるケースも多いと言えます。
胎児が頭位(頭が下向き)の状態にある
胎内で赤ちゃんが頭を下に向けた状態も、胎動を感じやすいでしょう。
これは赤ちゃんの足が上にあると、足伸ばしをしたときにママのおなかへ伝わりやすいからです。
胎動を感じにくい人の特徴
赤ちゃんの動きが少なかったり弱かったりすると、順調に育っているのか不安になるママもいるかもしれません。胎動を感じにくい場合、妊娠期や赤ちゃんの位置も関係してきます。
初産婦
初めて出産を経験する女性は、胎動を認識することにまだ慣れていません。
そのため、おなかの赤ちゃんの動きをキャッチできないことがあり、経産婦と比べると胎動を感じる時期が遅くなりがちです。
体脂肪が多い
体脂肪の多い妊婦は、胎動を感じにくい、または感じられない場合があります。
脂肪の厚みが、胎動の伝わりを妨げてしまうことがあるからです。
胎児が骨盤位(逆子)の状態にある
赤ちゃんや胎盤の位置によっても胎動は違ってきます。
なかでも骨盤位といって逆子の状態にある場合、赤ちゃんの手足は下向きになっているため、胎動は下腹部や足の付け根などで起こりやすく、赤ちゃんが頭位のときより感じにくくなります。
また、胎盤が子宮の前側にある場合は、胎盤の厚みがクッションとなり、赤ちゃんが動いても腹壁への伝わり方が弱くなるようです。
胎動での赤ちゃんの動き
赤ちゃんはさまざまな動き回りながら、ママのおなかの中で日々成長しています。
胎動として伝わる動きにはいくつかの種類があります。
手足の曲げ伸ばし(キッキング)
胎内の赤ちゃんが、手足を曲げたり伸ばしたりする行動がキッキングです。おなかに伝わる感触は、トントンと軽い刺激やポコポコと力強い刺激など、さまざまです。
おなかから手や足を元気いっぱいに伸ばしている際は、子宮をぐーっと押されるような刺激がママへと伝わるでしょう。
赤ちゃんが蹴ったところをトンと優しくたたいて合図して、赤ちゃんがまた同じところにキックしてくれるのを待つキックゲームを試してみても楽しいかもしれません。
手のひらの開閉
筋肉や神経が発達してくると、赤ちゃんが手のひらを閉開してグーパーする様子が見られます。
妊娠初期や中期では、手のひらの開閉を直接感じることは少ないですが、妊娠後期になると外側からわかるほどに、ママのおなかから赤ちゃんの手の形が飛び出す場合もあります。
身体の回旋と回転(ローリング)
赤ちゃんが身体をくるりと回したり向きを変えたりする動作をローリングと呼びます。
妊娠中期には、赤ちゃんの身体が上下や左右などに活発に回転する動きが見られるようになり、赤ちゃんが動くとママにもグルっといった感覚が伝わることが多いでしょう。
妊娠後期では子宮のスペースが狭くなるため、動く範囲も限られて上下の回転は減少し、左右の回旋が頻繁になっていくようです。
しゃっくり様運動
おなかの中で赤ちゃんがしゃっくりのようにドクンドクンと、一定間隔で動くことがあります。
これは赤ちゃんが羊水を飲み込んだり横隔膜を動かしたりと、呼吸の練習をしていると考えられています。
しゃっくり様運動は長い場合、30分以上続くこともありますが、赤ちゃんが苦しんでいるわけではないので、基本的には心配しなくても大丈夫です。
今しかできないコミュニケーションを楽しみましょう!
胎動は妊娠期や出産経験、ママの体型や精神状態などで感じ方が異なります。胎動を頻繁に感じると赤ちゃんとのつながりを感じ、愛おしさも増してくることでしょう。
胎動が少ない、弱いなど、少しでも不安があれば躊躇せずに、かかりつけの医師に受診して相談してください。また、妊婦健診で定期的に赤ちゃんの状態を確認することが大切です。
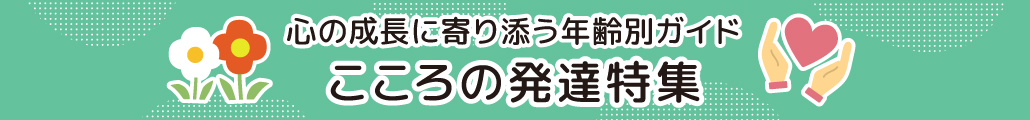

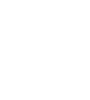










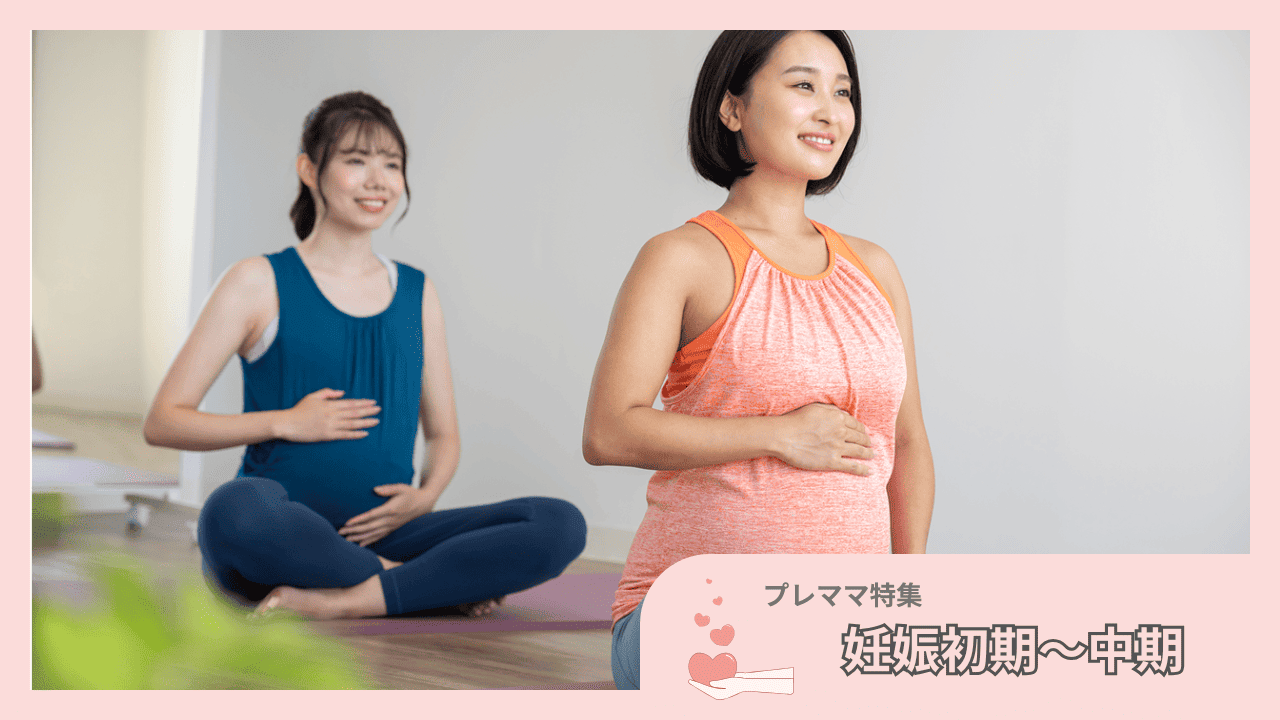












 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す