
5歳児といえば、「魔の2歳児」「イヤイヤ期」「4歳の壁」と呼ばれる時期を過ぎ、言葉で気持ちを伝えたり人の言うことを理解したりする力がついて、大きく成長を感じる年齢です。
しかし、5歳から小学校中学年(10歳)頃までは「中間反抗期」と呼ばれる時期でもあり、5歳頃の子どもは親に反抗したり、わがままを言ったり、癇癪を起こしたりしやすい傾向もあります。
今回は、5歳児の反抗期の特徴や対応方法などを詳しく解説します。

この記事を監修いただいたのは…
メンタルトレーナー/プロフェッショナル心理カウンセラー・アイディア高等学院学院長 浮世満理子さん

トップアスリートから経営者まで幅広い分野のメンタルトレーニング、カウンセリングを行うかたわら、心のケアの専門家の育成を目指し、アイディアヒューマンサポートアカデミーを設立。
また、子どもの可能性を引き出し、生きる力を育てる、アイディアメンタルトレーニング個別塾、アイディア高等学院も開設。著書、講演、マスコミ出演など多数。
5歳児の発育発達について
5歳児は保育園や幼稚園では1番上の年長クラスにあたり、年下の子のお世話をするような頼もしい成長もする頃です。
自分でできることも増え、ママやパパの家庭での負担も少しずつ減ってくる頃かもしれません。
しかし、まだ大人と同じようにはできないため、子どもがやりたい意欲はあるのにできないもどかしさを感じる時期でもあります。
また、言葉のやり取りも上手になるため、親の言うことに口答えをしたり、揚げ足を取ったりすることが増えやすいのもこの時期の特徴です。
イヤイヤ期との違い
「イヤイヤ期」は「第一次反抗期」とも呼ばれ、1歳後半から3歳くらいまでの子どもが言葉や態度で「イヤ(だ)」と反抗する時期を指します。
自我が発達してやりたい気持ちの芽生えた子どもが、思うようにできなかったり、気持ちを言葉で伝えられなかったりするときに「イヤ」という態度を表わすのです。
イヤイヤ期も5歳児の中間反抗期も、やりたい気持ちがありながら思うようにできないため反抗する点は似ています。大きな違いは、イヤイヤ期では子どもが「イヤ」という言葉・態度を前面に出すのに対し、5歳児の反抗期では「イヤ」以外の反抗的な態度を示すところです。
たとえば、5歳になると屁理屈をこねたり、わかったうえでわざと汚い言葉を使ったりすることもあります。
つまり、5歳児の反抗期はイヤイヤ期の延長線上にあり、発達が進んだことで反抗の仕方を変えたものと捉えられます。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★【心理カウンセラー監修】中間反抗期とは?
5歳児の反抗期にみられる特徴
言葉や思考力が発達した5歳児の反抗期では、それまでとは異なる行動がみられるため、ママやパパも対応が難しいと感じるかもしれません。
しかし、特徴を理解しておけば、適切な対応がしやすくなります。ここでは、この時期の反抗の特徴を3つ紹介します。
口答えをする
親に言われたことに対して、口答えをするようになるのが1つめの特徴です。
成長して口が達者になった分、屁理屈をこねたり、ママやパパを怒らせるように言い返したり、正論を言って大人を困らせたりすることがあります。
言葉遣いが悪くなる
2つめの特徴として、5歳児は言葉で反抗できるようになった分、わざと汚い言葉を使ったり、乱暴な言い方をしたりするケースもみられます。
友だちなど外からの影響で、汚い言葉を覚える場合もあるでしょう。悪いとわかっているのに、あえてよくない言葉を使ってみたい時期でもあります。
親の言うことを無視する
聞こえているのに聞こえないふりをするなど、無言の態度で反抗するのが3つめの特徴です。
気に入らないときや言葉で反論できないときに、返事をしなかったり黙り込んだりして、ママやパパの言うことを無視する場合もあるでしょう
状況に合わせた対応のコツ
子どもに口答えをされたり無視されたりすると、ついカッとなってしまうこともあるでしょう。しかし、感情に任せても解決しません。落ち着いて対処できるように、状況に合わせた対応のコツを解説します。
口答えをする場合
子どもが口答えをしたり言い訳をしたりするときは、子どもの話を途中で遮ったり否定したりせず、最後まで聞きましょう。
子どもはやみくもに反抗しているわけではなく、自分なりに主張しているのです。
まずは子どもの主張を理解して受けとめます。そのうえで家庭のルールや思いやりの心など、自分のことだけでなく、集団や相手を思いやる気持ちが大切なことを伝えましょう。
言葉遣いが悪くなる場合
子どもが乱暴な言葉を使っていても、同じような言葉で言い返したり怒鳴ったりせず、冷静に対応しましょう。
言葉遣いを正したいと思ったときは、すぐその場で「言い直し」をしてもらいましょう。
感情的にならずに、ただ「〇〇じゃなくて、なんて言うんだっけ?」と聞き直し、子どもに正しく言い直しをさせて、子どもから要求があっても飲まないことが大切です。
また、意味のない悪い言葉は、大人が反応しすぎないことが大切です。聞こえないふりなどをして、自然と言わなくなるのを待ちましょう。
親の言うことを無視する場合
子どもは無視しながらも、親の言うことを聞いているものです。返事をしなくても返事を強要したり、「ちゃんと聞いているの?」などと叱ったりせず、伝えるべきことを伝えたうえで、しばらく様子をみましょう。
そのとき子どもが遅れたり、何か不具合があったりしても、手を出して手伝うなどせずに、見守りつつも待つことが大切です。
男の子と女の子で反抗期の傾向は違う?
中間反抗期の特徴は個人差が大きく、性差だけで違いが生まれるわけではありません。
ただ、一般的に性別で出やすい行動の傾向があると言われます。
ここでは、参考までに男女ごとに出やすい中間反抗期の傾向について解説します。あくまで傾向なので性別で分けて考えるのではなく、自分の子どもに当てはまる行動に照らして、その対応方法を参考にしましょう。
男の子に多い特徴
一般的に男の子は、暴れる・叩くなど、言葉よりも行動で反抗するのが特徴です。ママやパパに対して暴力的な行為をするほか、物を投げる、叩く、壊そうとするなど身近なものにあたることもあります。
家庭内での暴力は、絶対許さないという強い姿勢で、家族のルールにすること。親が暴力で子どもを制圧するのはダメですが、子どもが物を壊したり、母親や妹など家族に手を上げたりしたときは厳しく叱ってください。
今、家庭内でそれを学ぶことで、小学校生活でのトラブルを未然に防ぐことができます。
女の子に多い特徴
一般的に女の子は言葉で言い返したり、屁理屈を言ったりすることが多い傾向にあります。ときには大人顔負けの理屈をこねて、ママやパパを困らせることもあるでしょう。
しかし、ここでも毅然と親として言うべきことは伝えてください。子どもが泣きながら言い返してくることがあっても、泣き止むのを待って伝えるべきことは伝えてください。
泣いたら大人が要望を叶えてくれると間違った学びをしてしまうと、小学校入学後の集団生活で困ってしまうことがあります。
【こちらの記事も読まれています♪】
★小学校の入学準備はいつから?
★「小1の壁」とは?
5歳児の反抗期のNG対応
反抗期を親子で乗り越えるためには、適切に対応することが重要です。よくない対応だと反抗期が長引いたり、その後の子どもの成長や親子関係に影響したりするケースもあります。ここでは、5歳児の反抗期に避けたい対応方法を紹介します。
ママやパパの意見を押し付ける
子どもは子どもの気持ちや考えがあります。たとえ子どもの主張が間違っていたとしても、否定してママやパパの意見を押し付けるのはやめましょう。
子どもの気持ちを受けとめて理解したうえで、社会には大切なルールがあること、それを守らないと自分が将来困ることを優しく諭してください。
感情的に怒りをぶつける
子どものあまりの態度に頭にきてしまい、感情的に言い返したくなることもあるでしょう。
しかし、反抗的な態度の裏には子どもの自立したいという気持ちや、どうにもならない葛藤が隠れているものです。子どもが感情的になっているときは、ママやパパは少し深呼吸をして心を整えるようにゆっくりと話してみてください。
子どもを突き放す
何を言っても子どもの気持ちが落ち着かないときは、しばらくそっとしておくことが必要な場合もあります。
しかし、「好きにしなさい」「もう知りません」などと突き放す言葉や態度はNGです。
「そんな子はうちの子じゃない」「生まなければよかった」など、子どもの人格を否定するような言葉も決して言ってはいけません。
「隣の部屋でゆっくり考えておいで」など、子どもが落ち着ける場所でただ静かに考える時間(サイレントタイム)を与えるのもひとつです。
【会員限定】親の気持ちがラクになる処方箋もご覧ください
キッズアライズの「親の気持ちがラクになる処方箋」では、子育てアドバイザーが子どもの困った行動の理由・対処法を解説中!
会員登録で全ての回答を見ることができます♪
調べるのも難しいけど、対応に悩んでいることはありませんか?
ママ・パパの息抜きにぜひご覧ください。
<質問例>
★何でも自分でやりたがる
→専門家の回答はこちら
★言わなくてもいいことを言う
→専門家の回答はこちら
★親をバカにしたり、見下したりする
→専門家の回答はこちら
▼▼すべての質問はこちらから見れます▼▼
子どもが自立するためのステップでもある
子どもは、成長するまでに何度か反抗期を迎えます。そのたびに親は大変な思いをするかもしれませんが、子どもが自立するためには必要なステップです。
一緒に乗り越えながらママやパパも親として成長し、親子で絆を強めていくことでしょう。
過ぎてしまえば、懐かしい思い出に変わるときがきます。子どもが反抗的な態度を取るようになったら、成長した証だと捉え、前向きに対応できるといいですね。
文:西須洋文
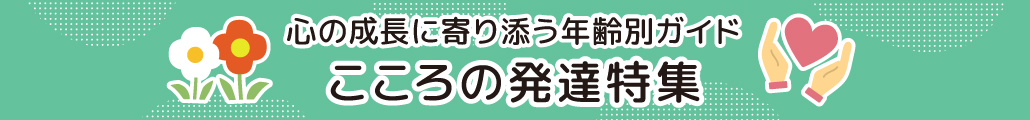

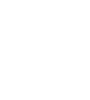










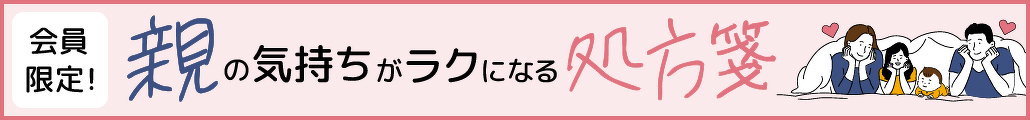






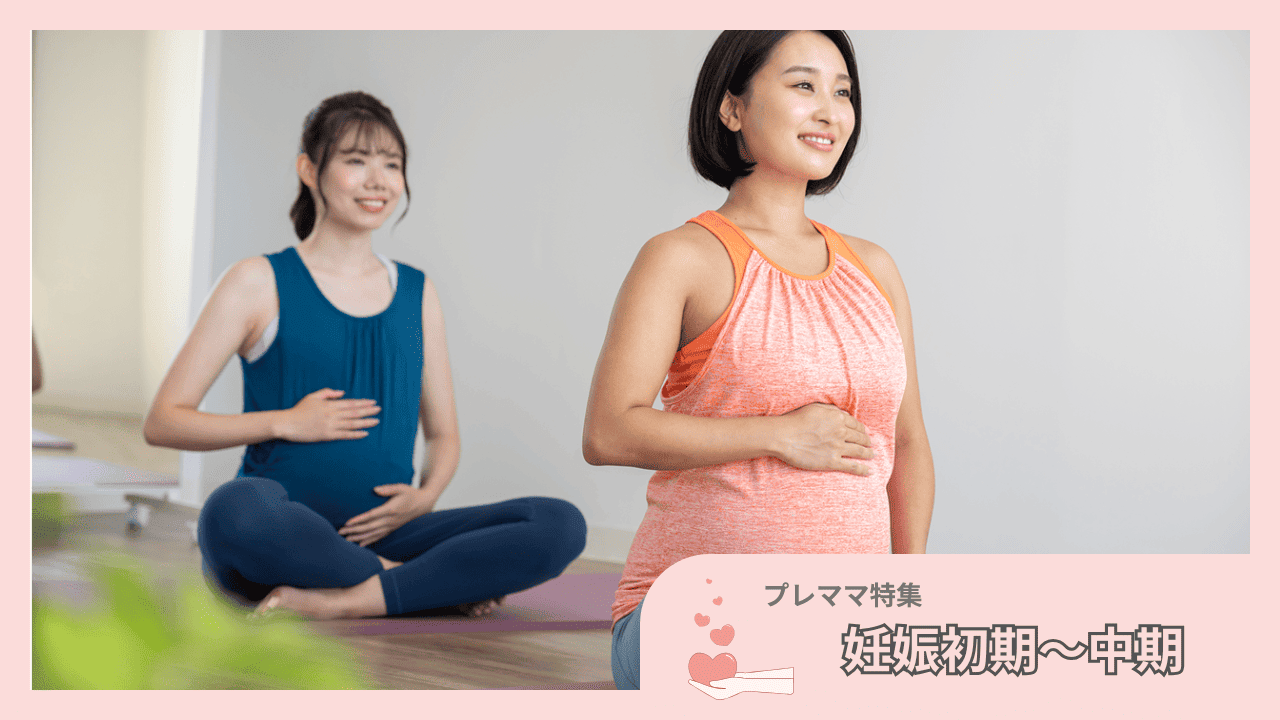

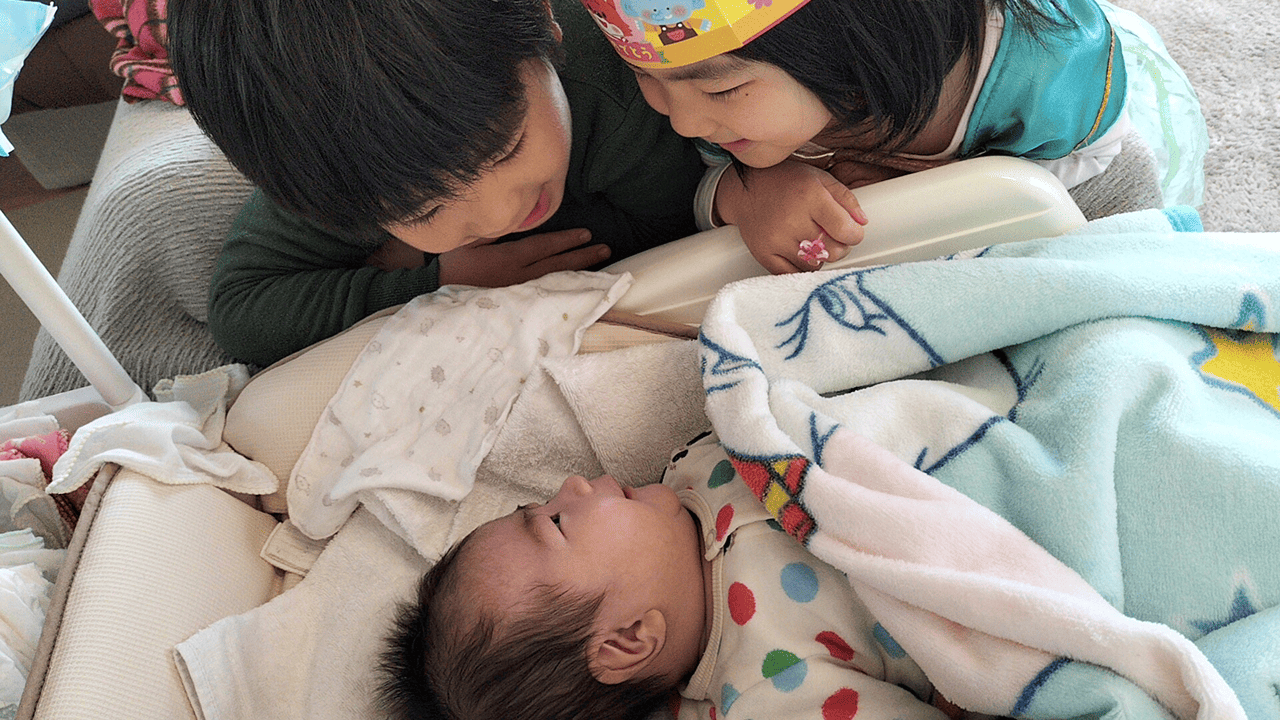





 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す