
小学校入学に向けて準備はできていますか?
今回は学用品など学校で必要な物の準備と、子どもがスムーズに学校生活を始めるために親子でしておきたい準備についてお伝えします。

小学校の入学準備はいつから?
小学校の入学準備といえば持ち物の用意を思い浮かべますが、それ以外にも準備しておくことはたくさん。
子どもが安心して小学校生活を送るための練習や心構えも、入学式までにしっかりチェックしておきましょう。
小学校入学説明会後に学用品を購入しましょう
一般的に1月下旬~2月の平日に、入学説明会が行われます。
まずはその資料をしっかり見て指定の学用品を用意しましょう。
また入学説明会では、入学までにお子さんに身につけて欲しいことの説明もあります。
できていないことがあれば、入学までにひとつひとつ練習しておきましょう。
【小学校入学準備】こちらも読まれています
その他の小学校生活に必要な道具は随時購入でOK
入学説明会で指示のなかった持ち物については、学校から案内があってから購入すれば大丈夫。
分度器やコンパス、リコーダー、水彩絵の具のセット、習字セット、彫刻刀セット、裁縫セット、エプロンなど、必要な時期が来たら購入しましょう。
入学に備えた持ちものの準備
入学に備えて購入するべきものの一例をご紹介します。
ランドセルの準備
最近の傾向で、ラン活(ランドセル購入)の時期は年々早くなっています。
人気のメーカーやデザインのランドセルを購入したい場合は、年中の秋ごろからカタログ請求などをし始めるようにしましょう。
また、メーカーの展示品や前年度のモデルは、アウトレット商品として、定価より安く販売していることもあります。
予算や子どもの好み、機能性なども考え、ランドセルを購入しましょう。
【ラン活について解説中♪】
★ラン活はいつから?基本のスケジュール
筆記用具や学用品の準備
必要な学用品は、入学説明会で渡される資料に書かれていることが多いです。
まずは資料を確認して、指定の学用品を用意しましょう。
また、一般的に必要な学用品は以下になります。
- 筆箱
- えんぴつ(黒・赤・青の3色)
- 消しゴム
- その他文房具(下敷き、のり、ハサミ、くれよん、色えんぴつ等)
- 科目ごとのノート(国語、算数、連絡帳、自由帳など)
- 連絡帳袋
- 給食用品(マスク、ランチョンマット、コップなど)
- 上履き
- 防災頭巾
- 雑巾
- 袋類(体操服袋、道具袋、給食袋、上履き袋など)
学校から指定がなくても用意しておくと便利な物
入学説明会で指定がなかった場合でも、以下のものを用意しておくと学校生活に役立ちます。
手提げ袋
- 大きめで丈夫なものを選びましょう。休み明けなど、荷物が多い日に使います。
- 子どもが好きなキャラクターのものや、電動のものを用意するといいでしょう。
- 通学路での安全対策として防犯ブザーや子どもの居場所が確認できるGPSなどを用意しておくと安心です。
- 着替えがしやすいように、上下セパレートタイプでストレッチがきいた素材の衣類がおすすめです。
使いやすい鉛筆削り
防犯ブザーやGPS
動きやすい衣類
【こちらの記事も読まれています♪】
★子どものスマホは何歳から持たせる?
入学前に身に着けたい学習習慣
ここでは、小学校生活で困らないように、学習面で練習しておきたいことを紹介します。
数に親しむ遊びをする
算数の土台となる「数の概念」を理解する経験をしておくと、入学後に算数の授業で教わる内容がスムーズに身につきます。
目安として0~20くらいまでの数が言えること、「全部で何個?」「右から何個目?」などがわかるようにしておくと安心です。
お風呂で数を数えたり、ままごとをしながら食べ物の数を数えたり、数を競うゲームで点数を数えたりと、いろいろな遊びの中で数に親しんでおくといいでしょう。
ひらがなの読み書きを練習
入学までに自分の名前が書けて、全部のひらがなが読めるように しておくといいでしょう。
書き順、細やかな筆の運びなどは入学後にひとつひとつ教えてくれます。
入学前には、細かなことを注意するより楽しく文字に親しめるようにしてあげることが大切です。
<こちらの記事で詳しく解説中>
★ひらがなの教え方のコツと練習法
机に向かって集中する時間をもつ
小学校の45分間の授業で落ち着いて座っていられるよう、家庭でも机に向かう時間をもちましょう。
することは、簡単なワークや迷路、ぬりえやお絵描きなど子どもが興味のあることで構いません。
30分程度を目標に、集中してできた時にはたくさん誉めてあげてください。
少しずつ授業に必要な集中力を養いましょう。
読書習慣をつけ音読の練習をしておく
小学校では、文章を読み取る力が必要になります。
いろいろな絵本に親子で親しみ、時には子どもが自分で読む練習をしておきましょう。
読書で培われる読解力は、さまざまな教科に生かせます。
子どもが興味のある本をいつでも手に取れるようにしておけば、読書習慣をつけやすくなりますよ。
【こちらの記事も読まれています♪】
★「音読」で得られるメリットと効果
入学前に身に着けたい生活習慣
身の回りのことを自分でする練習
小学校では、朝の準備や帰りの準備を子どもが自分で行います。
就学前から持ち物の準備は自分でするように練習しておきましょう。
体操服への着替え、脱いだ衣類をたたんでしまう練習、縄跳びや靴ひもなどのひもを結ぶ練習もしておきましょう。
自分の気持ちを言葉で伝える練習
小学校では、困ったことがあった時には子どもが自分から先生に伝えることが必要になります。
入学前から、自分の気持ちや状況を言葉で伝える練習をしておくと安心です。
普段から親が先回りして子どもを助けるのではなく、子どもが伝えてくるまで見守るようにしましょう。
時計の読み方を覚えて時間を気にして行動する練習
小学校では時間割に合わせて行動します。
時計の読み方を知っておきましょう。
「○時5分、○時10分…」と5分単位で読めるようにしておくと安心です。
また、時計を見て「何時までにやるべきことを終わらせる」という練習をしておきましょう。
食事を時間内に食べる練習
小学校の給食の時間は、幼稚園や保育園と比べて短く、入学後に焦ってしまう子も多いようです。
給食の時間として一般的な約20~30分で食事を終えられるよう練習しておきましょう。
また慣れていない食材に戸惑うことのないよう、魚や海藻類、豆類などいろいろな食材やメニューに慣れておくといいですね。
通学路や交通ルールの確認
安心して学校に行けるように通学路は事前に確認しておきましょう。
子ども自身が道を覚えられるまで繰り返しの練習が大切。
また登校班などがない場合は、通学路が同じ友達を見つけて一緒に登校する約束ができると理想的。
また、防犯ブザーはどんな場面でどのように使うのか、使い方を確認しておきましょう。
最近はデジタル化も進み、通学時の防犯対策として様々なアイテムが登場しています。
自宅や子ども部屋のレイアウト
学用品の家庭での収納場所を用意しよう
ランドセルや持ち帰ってくるプリントや教科書、体操服などの家庭での置き場を決めておきましょう。
置き場が決まっていれば、片づけの習慣がつきやすく、物をなくすことを予防できます。
学習環境を整えましょう
小学校に入学してからは、毎日の宿題等で家庭で学習をする時間が増えます。
子どもが勉強に集中できるように学習環境を整えることも大切です。
従来は、子ども部屋の学習机で一人で勉強するスタイルが一般的でしたが、近年は親の目の届く場所で学習することができるリビング学習も広く取り入れられるようになりました。
家庭の状況や子どもの性格に合わせて、良い方法を選択しましょう。
【こちらの記事も読まれています♪】
★リビング学習のメリットとレイアウトのポイント
小学校入学に備えた親の準備
学童保育の利用について
子どもが小学校入学を迎えるときに、放課後の預け先となる学童保育。
共働きや、子どもの入学を機に復職をする予定の家庭は、利用を考えていると思います。
学童保育の中にも、放課後児童クラブ(公立学童)、放課後子ども教室、民間学童など様々な種類があります。
それぞれ、預けられる時間や利用料が異なるため、どのような学童を利用するかを入学前に決めるようにしましょう。
【こちらの記事でも詳しく解説中】
★学童保育の料金の相場と減免制度
★小学生の放課後預かりの種類とポイント
小1の壁対策について
「小1の壁」とは、子どもが小学校に入学することで生じる子育ての仕事の両立が困難になる現象を言います。
小1の壁は、保育園と比べ学童保育の預かり時間が短くなることや、学校行事・PTA活動への参加、子どもの宿題や日常のフォローの大変さが原因となることが多いです。
「小1の壁」対策を家族で話し合い、対策を打つようにしましょう。
【こちらの記事でも詳しく解説中】
★小1の壁とは?原因と利用できるサービス
留守番や鍵の扱いについて
留守番は、小学1年生から徐々に任せていく家庭が多いです。
仕事だけでなく、親の通院や学校の保護者会など、子どもを連れていけないシーンも多いですよね。
留守番をいつから任せるようにするかや、留守番をさせる際のルール、防犯対策なども考えるようにしましょう。
【こちらの記事でも詳しく解説中】
★子どもの留守番は何歳から?注意点と防犯対策
★鍵っ子デビューはいつから?防犯対策を解説
親の前向きな言葉かけで小学校入学が楽しみに
最後に、入学準備でとても大切なのが「心の準備」。
子どもが「小学校、楽しみだな」と思えれば、いろいろなことに前向きに取り組み、小学校生活にもスムーズに慣れていきます。
心配なことがあるかもしれませんが、まずは親が「あなたなら大丈夫」「たくさんのお友達ができるよ」「小学校でいろいろな勉強ができるの、楽しみだね」など前向きな言葉をかけてあげること。
そうすれば、子どもは安心し笑顔で小学校生活をスタートできるはずです。
【キッズアライズおすすめ記事はこちら♪】
★小学校の登校時間は何時?出勤が早い時の対処法
★【体験談】小学校入学前の準備にハラハラ!
★小学校の入学式はいつ?当日の流れとマナー
ライター:nicoai
元保育士、幼児教室講師。
育児を楽しみながら、家族療法カウンセラー、チャイルドカウンセラーの資格を取得。
「子育て学び広場にこあい」で、オンライン子育て相談や子育て講座を開催しています。
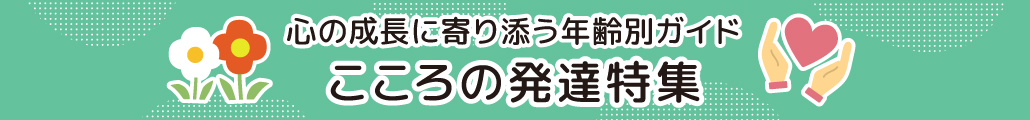

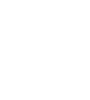







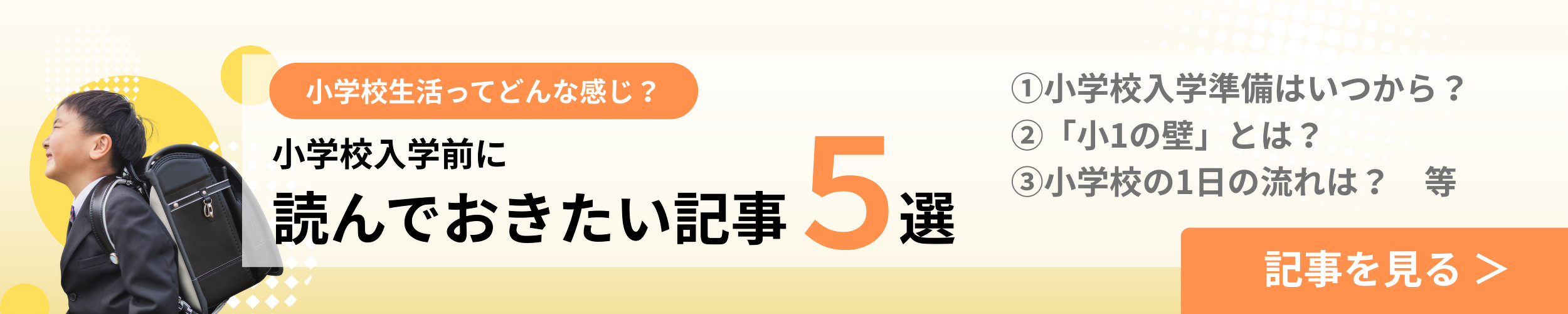












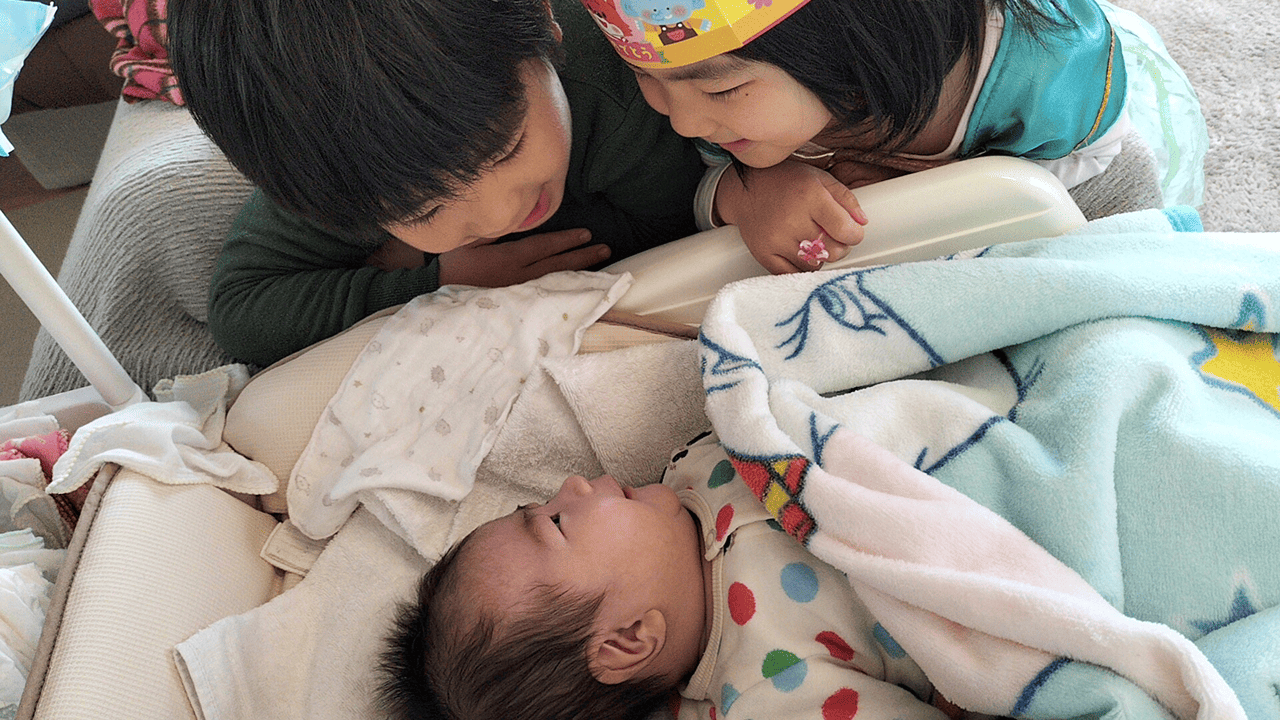





 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す