
子どもがママやパパに嘘をついたり、言い返したりすることが増え、戸惑うことはありませんか?
小学校中学年くらいで反抗的な態度が見られたら、もしかしたら「中間反抗期」かもしれません。
今回はプロフェッショナル心理カウンセラーの浮世満理子さん監修のもと、中間反抗期とはどのようなものなのか、どう対応したらよいのかを解説します。

この記事を監修いただいたのは…
メンタルトレーナー/プロフェッショナル心理カウンセラー・アイディア高等学院学院長 浮世満理子さん

トップアスリートから経営者まで幅広い分野のメンタルトレーニング、カウンセリングを行うかたわら、心のケアの専門家の育成を目指し、アイディアヒューマンサポートアカデミーを設立。
また、子どもの可能性を引き出し、生きる力を育てる、アイディアメンタルトレーニング個別塾、アイディア高等学院も開設。著書、講演、マスコミ出演など多数。
年長~小学校中学年に起こる中間反抗期とは?
“反抗期”と聞くと、2~3歳頃の子どもに見られる「第1次反抗期」や、小学校高学年~中学生頃に見られる「第2次反抗期」を思い浮かべる方が多いと思います。
「中間反抗期」とは、その第1次反抗期と第2次反抗期の間に起こる反抗期のことです。
年長から小学校中学年の間に起こると言われている反抗期
中間反抗期は、年長(5歳頃)から小学校中学年(10歳頃)に起こることが多いと言われています。
いわゆるイヤイヤ期とも言われる第1次反抗期や、思春期に起こる第2次反抗期と比べるとあまり知られていませんが、親に反抗的な態度を取ることはめずらしくありません。
また中間反抗期の中でも、特に小学校3~4年生頃は「ギャングエイジ」と呼ばれることもあり、友だちと仲間意識が強くなることで排他的になったり、男女間で対立したりすることが多くなる時期と言われています。
【こちらでも詳しく解説中♪】
★ギャングエイジの行動の特徴と関わり方のポイント
★5歳児の反抗期にみられる特徴
中間反抗期は子どもの発達の過程
中間反抗期も他の反抗期と同じく、子どもの発達において大切な時期です。
反抗するのは「自分で考えて行動したい」「ママやパパの意見に納得できないときは自己主張したい」という気持ちがあるからこそ。
自立のための時期と考えましょう。
また、この時期の子どもは、家庭から出て少しずつ外になじもうとしています。
親から独立しようとする時期、人間関係の構築を学ぶ時期でもあるため、見守る姿勢を意識してみてくださいね。
どのような反抗をするの?
中間反抗期の子どもには、以下のような行動が見られます。
- 口答えをする
- 嘘をついたり隠し事をしたりする
- 自分に都合のよい理屈を口にする
- 無視する
- 大人の干渉を嫌がる
- 自分でやりたがる(決めたがる)
- 親よりも友だちを重視する
もちろん、上記以外の行動で親に反抗する子もいます。
子どもをよく観察し、変化を感じ取ってくださいね。
中間反抗期の特徴3つ
中間反抗期の子どもが取る行動はさまざまですが、特に多いとされる特徴をお伝えします。
以下のような特徴が見られたら、中間反抗期が始まったと考えてよいでしょう。
特徴①干渉されることを嫌がる
この時期の子どもは、自分の考えを持つようになり、自己主張するようになります。
そのため、ママやパパに指示されることを嫌うのです。
また「自分で決めたい」「自分でやりたい」という気持ちが強くあるため、ママやパパの手助けや干渉を煩わしく思うこともあります。
特徴②友だちの存在が大きくなる
中間反抗期の子どもは友だちとの仲間意識が芽生え、つながりを強く意識し始めます。
そのため、家族よりも友だちを重視する傾向にあります。
「ギャングエイジ」と呼ばれる小学校3~4年生の頃には、グループを作り、独自のルールを作ったり、排他的になったりすることも。
心配になるかもしれませんが、人間関係の基礎を学び、社会で生きるためのスキルを身に付ける大事な時期ととらえましょう。
特徴③なんでも自分でやりたがる
子ども扱いされることを嫌がる時期のため、なんでも自分でやろうとします。
そのため、自分でできることをママやパパが先にやってしまうと「自分でやりたかった」「あとでやろうと思っていた」と癇癪を起こすこともあるかもしれません。
【きょうだい育児中のママパパに人気の記事】
中間反抗期の対応・声掛けのコツ
中間反抗期は親が何を言っても聞かず、話をしようとするほど反発したり無視されたりするなど、ママやパパにとっては辛抱の時期かもしれません。
実際、子どもの態度に根負けをして、迎合してしまっているケースも多く見られます。
大人でも子どもでも、人間は接した通りの人になります。
そのため、子どもを「できる子」として接することが大切です。
すると子どもは「自分はできる」「ママやパパもそう思ってくれている」と信じて困難なことにもチャレンジし、子ども自身で自分の行動を考えられるようになります。
反対に「できない子」として接すれば、余計に反発を繰り返します。
中間反抗期は、ママやパパが子どもと「どう接するか」腹を据えて考える時期でもあります。
ここでは「できる人として接する」ことに軸を置いた、中間反抗期の対応と声掛けのコツをお伝えします。
まずは子どもの話をじっくり聞いてみる
反抗的な態度が見られたときは、まず子どもの話に耳を傾けてみてください。
この時期の子どもは、大人の指示や干渉を嫌がります。
意見を押し付けず、子どもが話せるところから子どもの意見を聞き出しましょう。
おやつを食べているときや宿題を終えたあとなど、子どもがリラックスしているタイミングで要求を確認してみてください。
子どもにやりたいことがある場合、必要なことであればチャレンジさせてあげることも大切です。
中間反抗期の子どもは、反抗しつつも、実はまだママやパパに甘えたい時期。
親子2人で向き合い、子どもに「ママやパパはあなたのことをいつも考えている」と感じ取ってもらいましょう。
子どもに干渉しすぎないようにする
それまで大切にお世話してきたことを考えると難しいかもしれませんが、干渉しすぎない努力も必要です。
できるだけ口を出さず、見守ってあげましょう。
まだ年長~小学校中学年くらいであれば、上手にできないことも多々あります。
つい手を出したくなるかもしれませんが、上手くいかないことも大切な学びです。
チャレンジを続けるか、やめるかは子どもが決めるのを見守りましょう。
感情的にならずに、冷静に話をする
子どもが反抗的な態度を取ると、ママやパパは心配や苛立ちから感情的になりがち。
もし「ダメなことはダメ」と伝えなければならない場合は、なるべく冷静に話をするよう意識しましょう。
「散らかさないで」「早く着替えて」など指示するような口調は控え、「片付けてくれると助かるな」「早く準備したほうが気が楽だよね」などポジティブな声掛けを意識してみてくださいね。
暴言や暴力には毅然とした態度で対応する
この時期の子どもは、「ウザい」「キモい」など相手を傷付ける言葉を使うこともあります。
反抗心から暴力をふるってしまうタイプの子もいるかもしれません。
「暴言や暴力をふるったら親が言うことを聞いた」と学習したら、今度は自分の要求を通すために暴言や暴力をふるうようになります。
ママやパパは毅然とした態度で、暴言や暴力はいけないと伝えましょう。
受けた相手がどう思うか、自分がされたらどう思うかなどを問いかけ、話し合ってみてください。
【こちらの記事も読まれています♪】
★子どもが爪を噛むのはなぜ?原因と対処法
★子どものアンガーマネジメントと家庭でのサポート
してはいけないNG対応
中間反抗期の子どもは、自立に向かって成長している過程の中にいます。
成長の芽を摘み取らないよう、以下のような対応をしないよう気を付けましょう。
子どもの話を聞かずに決めつける
自分でやりたい、大人に決められたくない。
そんな時期の子どもの話を聞く前に、ママやパパの意見を押し付けたり「どうせできないんだから」「サボりたいだけでしょう」などと決めつけたりするのはNGです。
行動や意見を否定してしまうと、子どもは自信をなくし、劣等感を抱きやすくなります。
「あなたならできるよ」と自己肯定感を高める声掛けをしましょう。
子どもを突き放す
年長~小学校中学年頃の子どもは、まだママやパパとの関わりを求める時期です。
「もう知らない!」と突き放されてしまうと、深く傷つくことがあります。
反抗心が強まったり、本当の気持ちを隠すようになったりすることも。
話し合う時間を作り、子どもと向き合うことで「あなたのことを信じているよ」と伝えてくださいね。
【会員限定】親の気持ちがラクになる処方箋もご覧ください
キッズアライズの「親の気持ちがラクになる処方箋」では、子育てアドバイザーが子どもの困った行動の理由・対処法を解説中!
会員登録で全ての回答を見ることができます♪
調べるのも難しいけど、対応に悩んでいることはありませんか?
ママ・パパの息抜きにぜひご覧ください。
<質問例>
★子どもが約束を守らない!
→専門家の回答はこちら
★親をバカにしたり、見下したりする
→専門家の回答はこちら
★ゲームなどに負けるとすぐに泣く
→専門家の回答はこちら
▼▼すべての質問はこちらから見れます▼▼
中間反抗期でもまだ甘えたい年頃。寄り添うことを大切に
中間反抗期の子どもには、干渉しすぎないこと、感情的にならないこと、反抗的な行動が見られたときは話を聞くことが大切です。
家族よりも友だちとの関わりが増える時期ですが、反抗的な態度を取っていてもまだ幼い子どもであることは忘れず、気持ちは常に子どもに寄り添い見守りましょう。
ママやパパが一生懸命に向き合おうとしても上手くいかないことの方が多いかもしれません。
しかし、子どもが何を言っても、どんな態度をとっても、トライ&エラーで一貫してやり続けることが大切です。
子育てを通じてママやパパも一緒に成長する、そんな風に子どもの将来を見据えながら子どもとの関わり方を考えてはいかがでしょうか。
文:あまね
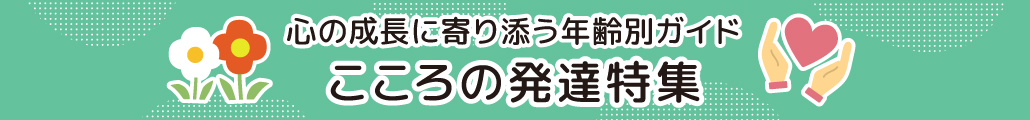

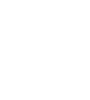







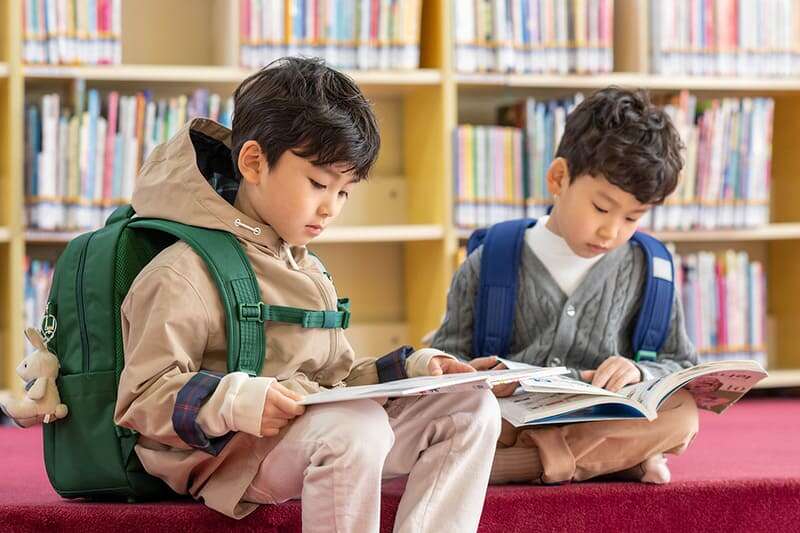

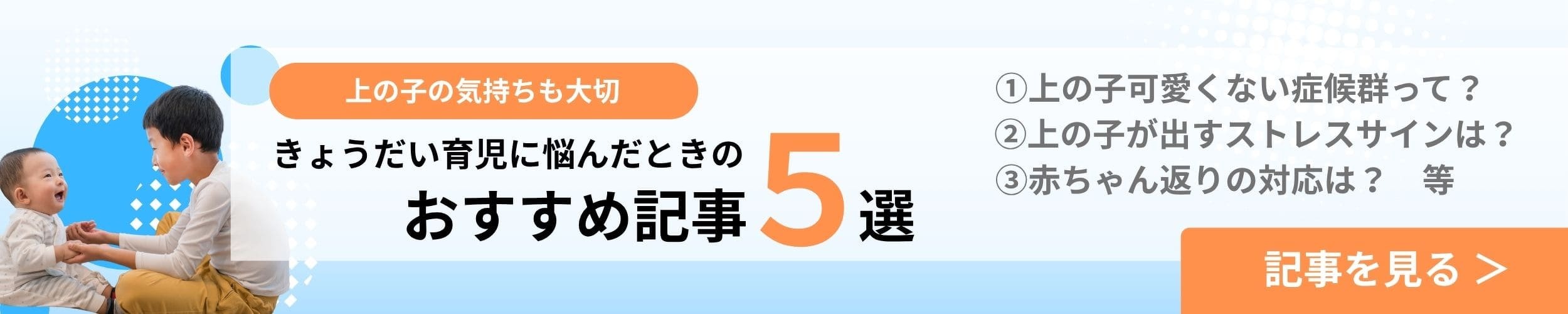


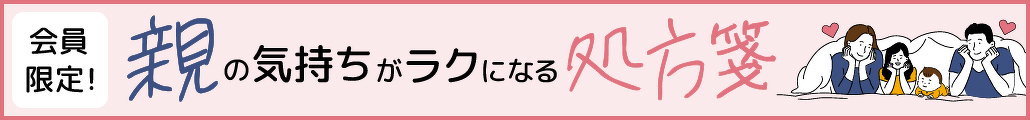














 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す