
赤ちゃんが母乳やミルクをたくさん飲めるようになるのはとても嬉しいことですが、与える量や授乳間隔の判断が難しいときもありますよね。今回は、新生児期(生後28日未満)の赤ちゃんにみられる母乳やミルクの飲み過ぎの症状、空腹と満腹のサインとその対応について解説します。

この記事を監修いただいたのは…
助産師:古谷 真紀(ふるや まき)さん
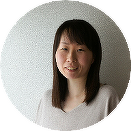
自治体や企業等と連携した産前産後ケア事業担当を歴任後、妊娠中から産後のママパパ&赤ちゃんのための講座運営や相談事業に従事している。
新生児期の赤ちゃんの「飲み過ぎ」とは?
赤ちゃんの「飲み過ぎ」とは、必要な量を上回るほど飲んだり、消化できる以上の量を飲み続けたりして、急激な体重の増加を引き起こすほどのエネルギー(カロリー)を摂取している状態を指します。
赤ちゃんが必要とする授乳の量や回数は月齢、体重、食欲などによって異なります。特に新生児期の赤ちゃんは胃が小さく、急激に成長するため、少ない量を頻繁に飲むことで栄養や水分を補う必要があります。
一般的に示されている授乳の目安を超えているからといって、必ずしも「飲み過ぎ」とは限りません。
しかし、空腹以外のときも授乳すると、食欲が旺盛な赤ちゃんは満腹感を感じにくくなり、飲み過ぎることがあります。
また、授乳が気持ちを落ち着かせる唯一の方法になると、授乳しないと眠れない習慣がつくことがあります。
将来的に食事でストレスを解消しようとしたり、体重が増え過ぎるリスクが高まるため、飲み過ぎが習慣にならないように気をつけることが大切です。
赤ちゃんは飲み過ぎるとどうなる?
通常、必要以上に飲んでも余分な栄養は吸収せずに吐き戻したり、便として排泄したりしますが、他にもいくつかの症状が同時に現れるときは飲み過ぎている可能性があります。
赤ちゃんが飲み過ぎたときに現れる症状
- よく吐き戻す
- よくいきんだり、うなったりする
- 授乳中にむせる
- 泣いたり、ぐずったりなどの不機嫌が続く
- 咳や鼻詰まりなど風邪のような症状が続く
- お腹が張る
- 頻繁にげっぷやおならをする
- 便秘あるいは泡立った軟らかい便が出る
- 体重が急激に増える
過飲症候群とは?
数日から数週間にかけて飲み過ぎの状態が続くと、過飲症候群(別名:飲み過ぎ症候群)になることがあります。
飲み過ぎの症状に加えて、通常よりも体重が増える量が多い、生後1か月頃によくみられるケースの総称です。
症候群といっても病気ではありません。
飲み過ぎを防ぐためには、赤ちゃんの空腹と満腹を見極める、授乳の方法を見直す、授乳の途中でげっぷを促す、哺乳瓶の乳首のサイズを変えるなど、ちょっとした工夫で解決することが多いです。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★新生児の体重増加の目安と量り方
空腹のサインと満腹のサイン
赤ちゃんは空腹や満腹を感じると、いくつかのサインで知らせます。
空腹のサイン
お腹が空き始めると、まずは口の周りの動きが目立ち、もっと空腹になると全身の動きも増えます。
1つのサインだけでは空腹を判断することは難しく、泣くことが必ずしも空腹を意味するわけではありません。
空腹で泣く場合には、他のサインも同時にみられることが多いです。
- 手を口や顔に近づける
- 口や顔に触れるものの方向へ顔を向けて口を開ける
- 手足を動かす
- 吸うように口を動かしたり、音を出したりする
- 胸やお腹の上でこぶしを握り締める
- 「ウー」「クー」「ハー」など小さく柔らかい声を出す
満腹のサイン
満腹のサインを見逃すと、赤ちゃんは満腹でも飲み続けてしまうことがあります。
満腹のサインがみられたら、無理に飲ませないようにしましょう。
- 頻繁に飲んだり止めたりを繰り返す
- おっぱいや哺乳瓶から口を離す
- 飲むスピードが遅くなる
- ぼんやりしたり、眠ったりする
- そわそわしたり、気が散りやすくなったりする
- おっぱいや哺乳瓶が近づくと口をギュッと閉じたり、顔をそむけたりする
【0歳児ママ向け】こちらの記事も読まれています
赤ちゃんの食欲は調節できる?
WEB上には「生後◯か月で満腹中枢が完成する」「満腹になると飲まなくなる」といった情報が広まっていますが、これを裏付ける医学的な根拠は今のところありません。
母乳やミルクを飲む量を調節する能力は、赤ちゃんによって大きく異なります。
この食欲を調節する能力は胎内で発達が始まり、生後数週間から数か月の間にさらに発達します。
赤ちゃんの食欲には遺伝的な要因が影響することが科学的に示されていますが、食欲は遺伝子だけで決まるものではなく、生まれて間もない時期からの授乳の経験も大きく影響することがわかっています。
【こちらの記事も読まれています♪】
★魔の3週目とは?起こる要因と対処法
★モロー反射はいつまで?原因と対処法
★沐浴の卒業タイミングはいつ?
赤ちゃんの授乳に対する反応のタイプと対応のヒント
過去に行われた国内外の調査では、新生児期の赤ちゃんの授乳に対する反応は、主に5つのタイプに分類されています。
また、いくつかのタイプが組み合わさることもあります。
空腹と満腹のサインだけでなく、どのタイプに当てはまるかを知ることで、授乳をより楽しむためのヒントが得られるでしょう。
しっかり吸いつくタイプ
おっぱいや哺乳瓶が近づくとすぐに吸い始めるタイプです。
飲み終わってからもおしゃぶりのように吸い続けるときは、赤ちゃんが自然と離すまで授乳を続けるか、赤ちゃんの口の中にママやパパの指を入れ圧抜きをして離しましょう。
特に哺乳瓶は搾乳やミルクの流れの調整が難しいため、満腹でも飲み続けてしまうことがあります。飲み終わるタイミングを見極めることが大切です。
こだわりが強いタイプ
飲んでいる途中に、興奮して吸いついたり、離れたり、泣きわめいたりするタイプです。
なかなか吸いつかないときは抱っこなどで落ち着かせてから飲ませましょう。
このタイプは、ある程度授乳の間隔を予想して、空腹のサインを参考に、泣きだす前に授乳を開始することが効果的です。
後回しにするタイプ
授乳にあまり興味を示さず、眠りがちで、授乳を後回しにするタイプです。
抱っこしてもなかなか飲んでくれない場合は、焦らずに赤ちゃんが「飲みたい」と思うまで待ちましょう。
足の裏をくすぐる、おむつを交換するなど目覚めさせる工夫が必要です。
授乳間隔が4時間以上空かないように注意しましょう。
じっくりと味わうタイプ
飲み始めから遊んで飲むことが多いタイプです。
しばらく味見や抱っこを楽しんでから、ようやく本格的に吸い始めます。
無理に急かすと泣いてしまうこともあるので、赤ちゃんが遊んでいる間は見守り、しっかり吸い始めるまで待ってあげましょう。
のんびり飲むタイプ
飲み始めるとすぐに眠ってしまうことが多く、1回で飲む量が少ないタイプです。
飲んでは休むを繰り返すため授乳の間隔が短く、回数が多くなることがあります。
このタイプは、ママやパパも焦らずのんびり対応しましょう。
親子で授乳に集中できる環境を整えたり、家族で役割を分担することが大切です。
母乳を与える場合でもママの休息する時間を確保するために、他の人が授乳できるように搾乳を保存しておくとよいでしょう。
赤ちゃんが飲み過ぎかもと思ったら
飲み過ぎについて心配になったら、以下の対応をしましょう。
医師・助産師・保健師へ相談する
まずは専門家へ相談しましょう。
相談する際に、授乳、睡眠、排泄のリズムを簡単に記録したアプリやメモがあると便利です。
毎日記録をしておくことで、赤ちゃんの行動パターンやタイプを把握することができ、相談後の授乳方法の判断にも役立ちます。
空腹のサインと満腹のサインを再確認する
赤ちゃんが本当に空腹かどうかを判断せずに「欲しがるときに欲しがるだけ」という言葉をそのまま受け入れて授乳を続けると、実際には「飲みたいとき以外にも飲んでいる」状況になりがちです。
また、飲むスピードが速過ぎたり、空気を多く飲み込んだりすると、満足感が得られないこともあります。
授乳の間隔を空けずに何回も欲しがる様子がみられるときは、空腹と満腹のサインを再確認しましょう。
授乳の方法を見直す
赤ちゃんの授乳に対する反応のタイプを参考にしながら、授乳の姿勢や与える量、タイミングを見直してみましょう。
ちなみに、ミルクのパッケージに記載されている量は、ミルクだけで育つ赤ちゃんのための目安です。
早く生まれた赤ちゃんや小さく生まれた赤ちゃん、母乳を飲んでいる赤ちゃんは、必ずしも記載されている通りに飲む必要はありません。
また、授乳の途中に満腹のサインがあれば飲み干すまで与える必要はありません。
【授乳についておさらいしましょう♪】
★母乳の正しいあげ方
★基本のミルクの作り方・飲ませ方
★混合授乳の方法とミルク量
赤ちゃんの「飲み過ぎ」が気になったら相談しましょう
生まれたばかりの赤ちゃんにどれくらいの量を与えるべきかを判断するのは、ママやパパにとって難しいことがあります。
赤ちゃんが順調に育っていれば、授乳の量や回数にこだわり過ぎないことも大切です 。
もし飲み過ぎについて心配がある場合は、産後の2週間健診や1か月健診、または自治体が行う産後訪問の際に専門家へ相談しましょう。
【参考文献】
橋本武夫 母乳育児支援の再考学~過飲症候群~ ペリネイタルケア 37(6) 574-577 2018
Is Your Baby Hungry or Full? Responsive Feeding Explained American Academy of Pediatrics(2025年3月閲覧)
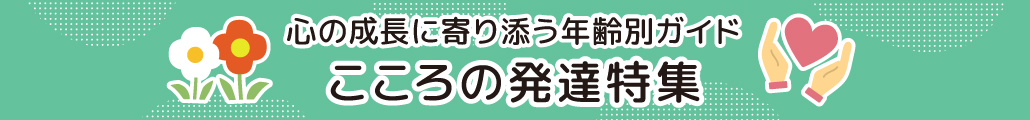

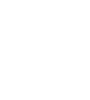








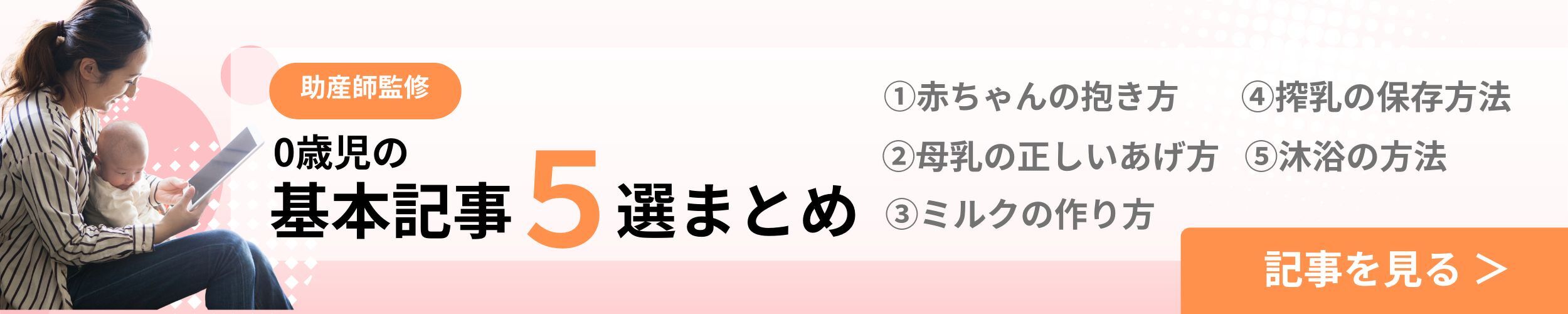


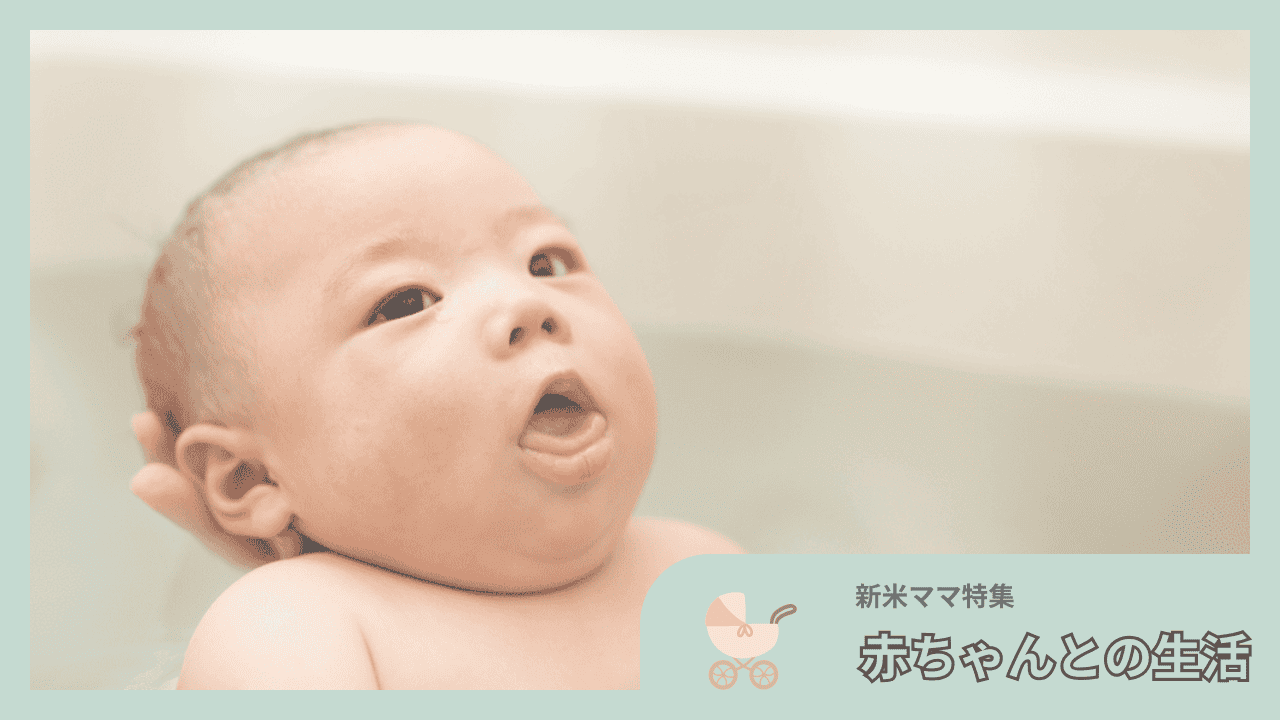











 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す