
赤ちゃんが生まれて1か月たつと、発達や成長をチェックする1か月健診が行われます。
1か月健診とはどんなことをするのか、また赤ちゃんと健診に出かけるときに準備するものや事前に確認しておいたほうがよいことを解説します。

この記事を監修いただいたのは…
助産師:古谷 真紀(ふるや まき)さん
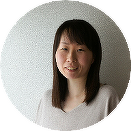
妊娠中から産後のママパパ&赤ちゃんのための相談事業を中心に活動中。
一般社団法人産前産後ケア推進協会プロジェクトリーダーとして、自治体や企業、団体と連携した産前産後ケア事業等を担当。
同協会が開設した訪問看護ステーションco-co-ro(東京都渋谷区)で、産前産後や子育て中のママのこころのケアを中心とした訪問看護にも従事。
赤ちゃんの1か月健診は何をするの?
1か月健診は、赤ちゃんの成長や発達をチェックして、病気が隠れていないかを確認する目的で行う健康診査(健診)です。
赤ちゃんの診察だけではなく、親の子育てに関する悩みや心配事を相談できる場です。
多くの場合、出産した医療機関で受けられます。
最近は、生後2週間健診を実施する医療機関も増えつつありますが、今回は多くの親子が受診する1か月健診の主な内容を解説していきます。
問診
問診では、
・授乳方法(母乳、混合、ミルク)
・授乳の状況(授乳間隔、量や回数など)
・排泄の状況(便や尿の色や形状、回数など)
・1日の生活リズム(睡眠や泣きなど)
について質問を受けます。
赤ちゃんの様子やお世話について、確認したいことや心配なことがあれば気軽に相談しましょう。
身体測定
身体測定では、赤ちゃんの体重、身長、頭囲などを計測します。
計測した数値は、母子健康手帳に記載されます。
医師による診察
赤ちゃんが順調かつ健康に育っているかを調べるために、医師が視診、聴診、触診をして赤ちゃんの全身の状態をチェックします。
心雑音や湿疹などの有無の確認、へそに異常が生じていないか、音や光への反応があるか、手足をよく動かすかなど運動発達の観察をします。
ビタミンK2シロップの投与
赤ちゃんに起こりやすい出血を防ぐため、血液を固める作用のあるビタミンKを含むビタミンK2シロップを複数回に分けて投与します。
計3回内服させる方法(3回法)と、13回内服させる方法(3か月法、13回法)があり、3回法で内服している場合は、1か月健診時に3回目の内服があります。
生まれて間もない時期に受けた検査の結果説明
新生児先天性代謝異常等検査(新生児マススクリーニング)や、新生児聴覚検査(新生児聴覚スクリーニング)の結果説明、生まれて間もない時期に検査を受けている場合はそれらの結果説明などがあります。
子育てに関する相談
必要に応じて、赤ちゃんのことや子育て、授乳に関する相談ができます。
赤ちゃんとの生活が始まったばかりで、授乳や夜泣きへの対応など、子育てに不安を感じることが多い時期です。
また、ママ自身は産後の身体の回復がままならず、睡眠不足になりやすく、気分が落ち込みやすい時期でもあります。
どんな些細なことでも大丈夫。
気軽に相談してみましょう。
持ち物は何が必要?
1か月健診での一般的な持ち物を紹介します。参考にしてみてくださいね。
<健診を受けるために必要なもの>
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- 乳幼児医療費受給者証(子ども医療費受給者証)
- 乳幼児健康診査受診票(自治体が1か月健診を公費負担の対象としている場合のみ)
- 診察券
- 問診票(事前に渡されている場合のみ)
- 健診の費用
<赤ちゃんに必要なもの>
- 着替え 1~2セット
肌着1枚+ベビー服1枚で1セット。
おむつ交換時や吐き戻しなどで汚れた際に着替えるため - おむつ 最低でも3~5枚
診察中に排泄することもあるため少し多めにあると安心 - おしりふき
おむつ交換時だけでなく、ウェットティッシュの代用としても使えるため便利 - 使用済みのおむつや汚れた衣類を持ち帰る袋
ビニール袋が数枚あると安心 - ガーゼ 1~2枚
授乳時やよだれを拭く時に使用 - おくるみor大きめのバスタオル
体温調整や日除けのために使用
<授乳時に必要なもの>
- 授乳ケープ
母乳を与える場合は必要に応じて持参。
授乳室があればなくてもOK - 哺乳びん
母乳だけで育てている場合は不要 - 育児用ミルク
粉タイプor固形タイプのどちらでも - 調乳に必要なお湯
医療機関が提供してくれる場合は持参不要 - (液体ミルクを製品の容器のまま与える場合は)専用の乳首
赤ちゃんについて質問や確認したいことがあれば、それについて記録した日記やメモ、アプリを登録したスマホなどを忘れず持参しましょう。
持ち運びには大容量かつ機能的なマザーズバッグがおすすめ
マザーズバッグとは、赤ちゃんとのお出かけの際に持っていくバッグのことです。
健診には多くのものが必要なので、大容量でたくさん入ることが重要です。
使い勝手のよいマザーズバッグで、快適な健診をしてくださいね!
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★新生児~1歳までのマザーズバッグの中身
【0歳児ママ向け】こちらの記事も読まれています
1か月健診にかかる費用は?
赤ちゃんの1か月健診にかかる費用は、保険診療外のため自費、つまり自己負担となります。
自治体によっては、受診した分の費用を助成する制度(公費負担)を設けていることがあります。
費用は医療機関によって異なりますが、5000円前後でおさまることが多い傾向です。
健診の際に、薬の処方など保険診療を受けた場合、健診とは別に費用が発生することがあります。
保険証や乳幼児医療費受給者証(子ども医療費受給者証)が手元にある場合は必ず持参しましょう。
1か月健診が公費負担の対象となる自治体に居住していて、里帰り出産などで居住する地域以外の医療機関で健診を受けた場合は、後日、居住する自治体へ申請すると払い戻し(償還払い)を受けることが可能です。
健診にかかる費用について、詳しく知りたい場合は、健診を受ける医療機関へ問い合わせましょう。
また、自治体による公費負担の制度については、居住する自治体の公式ホームページあるいは担当窓口等で確認してみてくださいね。
(※2023年4月時点の情報)
服装はどうする?
赤ちゃんの服装は、診察や測定の際に裸に近い状態にするため、着脱しやすい前開きタイプがおすすめです。
着せる枚数は、肌着1枚+ベビー服1枚で、普段から着慣れている服でかまいません。
また、おくるみが1枚あると、肌寒い時に保温したり、日差しの強い季節に日除けになるので便利。
大きめのバスタオルで代用してもよいでしょう。
必要に応じて授乳をしたり、移動したりするので、ママも動きやすく授乳しやすい服装がおすすめです。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★【気温別】赤ちゃんの服装の選び方
赤ちゃんをどう連れていく?
生まれて間もない赤ちゃんと長時間外出する1か月健診を控えて、緊張するママもいることでしょう。
徒歩圏内であれば、抱っこひもとベビーカーのどちらも適しています。
電車やバス、タクシーなど公共交通機関を利用する際、ベビーカーを使った乗り降りを負担に感じるのであれば、抱っこひもを使用しましょう。
健診を受ける医療機関が広い場合、移動の負担を考えるとベビーカーのほうが便利でしょう。
抱っこひもは対面して縦抱きするタイプを、ベビーカーは赤ちゃんを寝かせた姿勢のまま移動できる、新生児期から使えるタイプを使用しましょう。
自家用車で移動する場合は、必ずベビーシート(新生児乳児専用のチャイルドシート)を使用しましょう。
1か月健診の際に安心して使用できるように、抱っこひもやベビーカー、ベビーシートは事前に使用方法の確認と練習をしておくといいですね。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★新生児はタクシーに乗れる?チャイルドシートは?
★車にチャイルドシートを取り付けるときの注意点
1か月健診後にできるようになること
赤ちゃんの1か月健診が無事に終わると、沐浴を卒業して大人と一緒のお風呂に入ってかまいません。
赤ちゃんとのスキンシップにもなり、より身近に感じられるでしょう。
1か月健診を終えるまで外出してはいけないという決まりはありませんが、1か月健診を終えた頃から、自宅周辺の散歩や買い物など、外出する機会を増やす親子も少なくありません。
赤ちゃんは大人に比べて抵抗力が弱いので、季節や時間帯を選び、感染症が流行する時期は人混みを避けて、親子で外出することに少しずつ慣れていきましょう。
1か月健診を終えたら、次は生後2か月頃からワクチンデビュー、その次は3~4か月健診へ続きます。
乳児健診は、親が気づいていない成長や発達の変化を見つける目的もありますので、適切な時期に受けるようにしましょう。
不安を解消して赤ちゃんとの生活を楽しんで
赤ちゃんの1か月健診は、ママも初めてのことが多く緊張してしまいますよね。
1か月健診が無事に終われば、赤ちゃんとお風呂に入ったり、一緒にお出掛けを楽しんだり、できることも増えていきます。
この機会に、子育ての不安や悩みを相談して解消しましょう。
ライター:山村智子
4歳の男女双子と0歳の男の子の3児の母。ドタバタ育児の合間にライターをしています。せっかちでおっちょこちょいな性格なので失敗も多いですが、目標は「肝っ玉母ちゃん」。笑って過ごす日々を心がけています。
【参考文献】
・厚生労働省 母子健康手帳 省令様式(令和5年4月1日施行)
・国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 改訂版乳幼児健康診査 身体診察マニュアル 2021年3月
・水野 克己 『新版 お母さんがもっと元気になる乳児健診: 健診を楽しくすすめるエビデンス&テクニック』メディカ出版 2020年
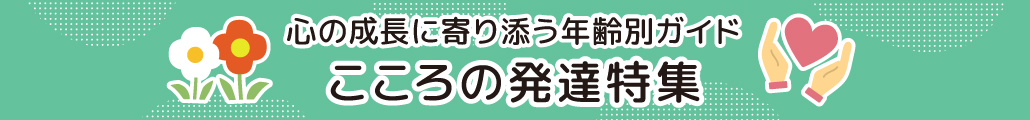

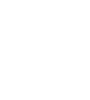








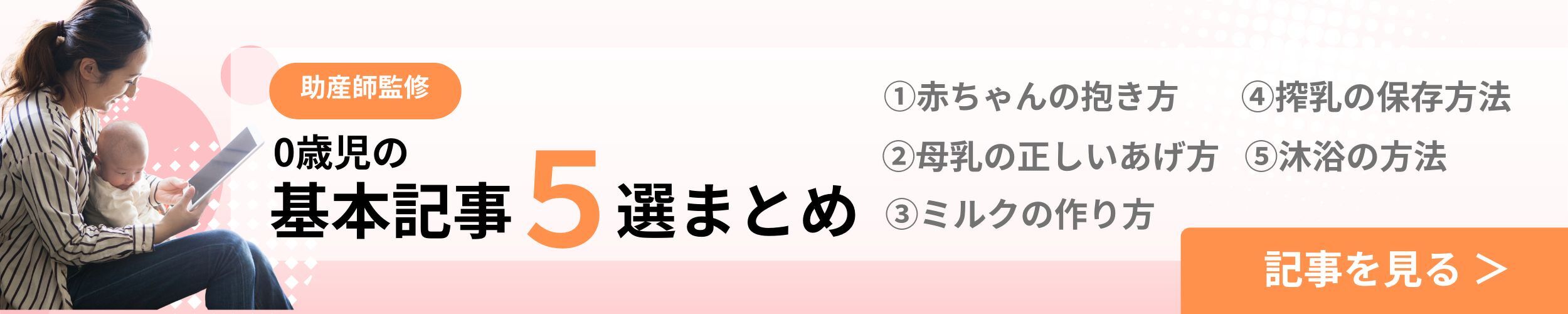





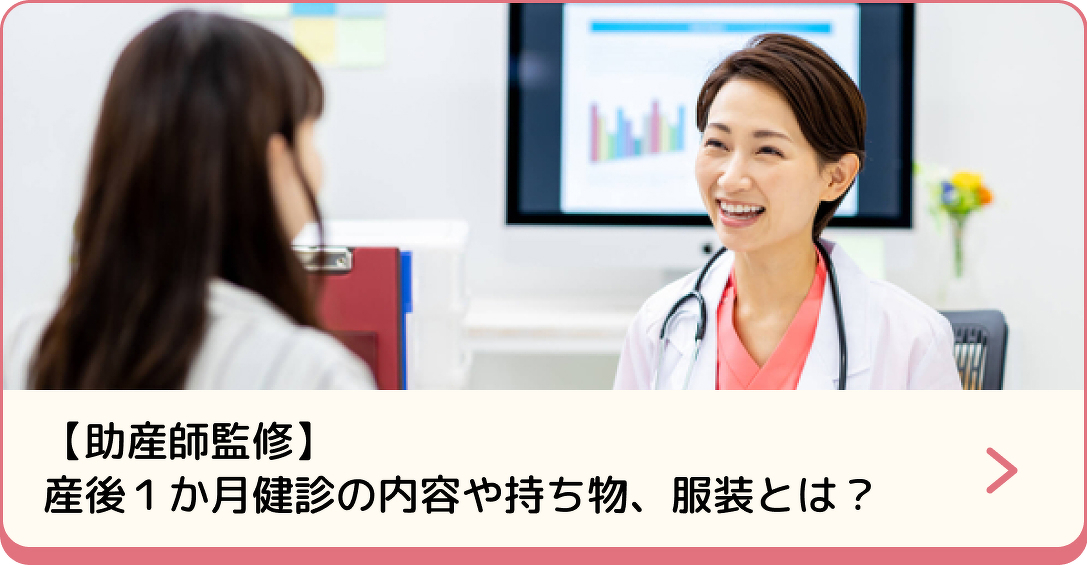


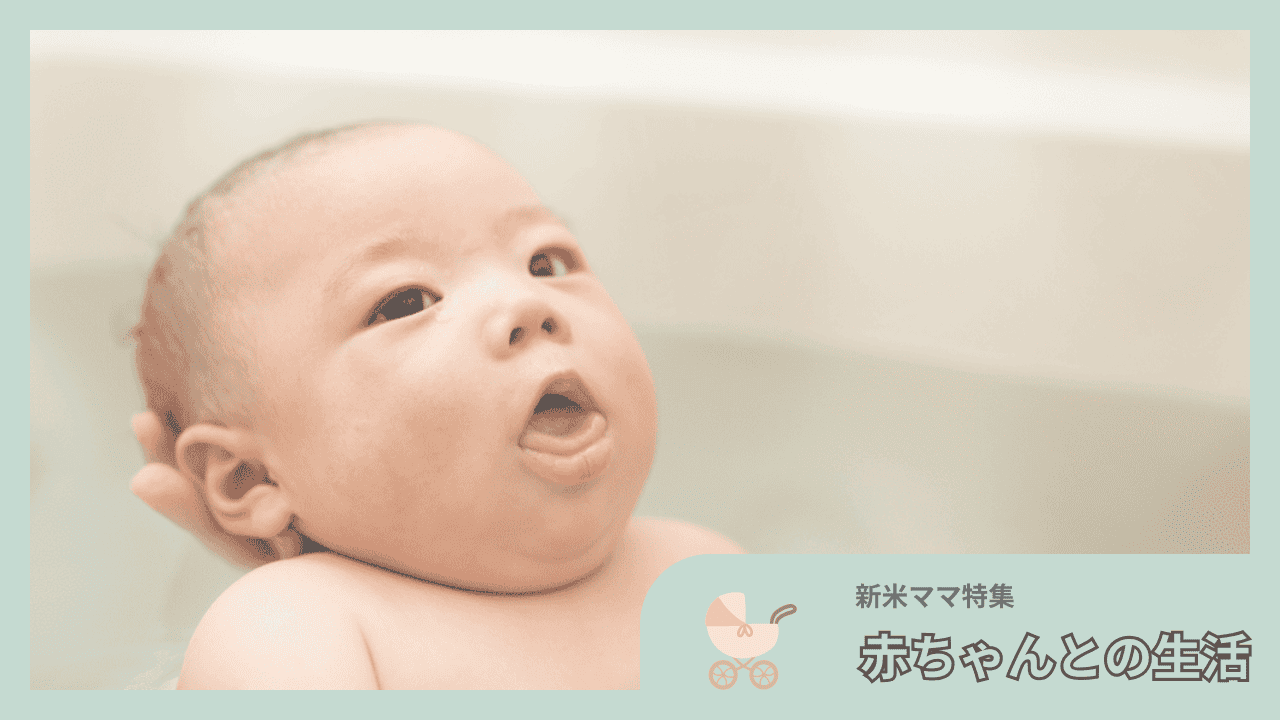










 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す