
赤ちゃんにとって睡眠をたっぷりとることは、心身の健やかな成長に欠かせません。しかし睡眠時間やリズムは赤ちゃんによってさまざまです。この記事では、Child Health Laboratory代表で医師の森田麻里子さん監修のもと、赤ちゃんの理想的な睡眠時間について、月齢ごとの一般的な目安を解説します。

この記事を監修いただいたのは…
チャイルドヘルスラボラトリー代表・医師 森田麻里子さん

東京大学医学部医学科卒。麻酔科医として勤務後、2017年の第1子出産をきっかけに2018年より子どもの睡眠の専門家として活動。
2019年昭和大学病院附属東病院睡眠医療センター非常勤勤務を経て、現在はカウンセリングや育児支援者・医療従事者向け講座、企業と連携したアプリ開発、コンサルタント育成などを行う。
赤ちゃんの理想的な睡眠時間
一般的に赤ちゃんはどれくらいの時間寝るのが理想なのでしょうか。
0~1か月の睡眠時間
生後0~1か月ごろはママのお腹の中から外の世界に適応するための期間です。このころの理想的な睡眠時間は、1日14時間~17時間ほど。
この時期は消化器官も未熟で一度にたくさんの量を飲めません。
授乳のタイミングで目覚めることも多く、昼夜問わず寝たり起きたりを繰り返します。1回に寝る時間もバラバラで、日によっても異なります。
2~3か月の睡眠時間
生後2~3か月ごろになると、赤ちゃんはだんだんと昼夜の区別がつき始めてきます。
そのため昼に起きている時間が増え、徐々に夜にまとまって寝るようになります。
このころの理想的な睡眠時間は1日14~17時間ほどです。
お昼寝はまだ一定ではなく、細切れのこともあれば、まとまって長く寝ることもあります。1回にまとまって寝る場合は、お昼寝が2~3回になることもあります。
4~6か月の睡眠時間
生後4~6か月ごろになると、昼夜の区別がしっかりつくようになります。
夜の睡眠時間は10~12時間ほど、トータルで12~16時間ほど眠るのが理想的です。
お昼寝はまだ細切れの日もありますが、徐々に3回程度にまとまっていきます。
午前に1回、午後の早い時間に1回、夕方にも短いお昼寝を1回するのが目安です。
7~12か月の睡眠時間
生後7~12か月ごろになると運動能力も発達し、よく体を動かすようになります。
夜の睡眠時間は10~12時間、1日トータルの理想的な睡眠時間は12~16時間ほどです。
お昼寝は3回程度から徐々に2回に減り、9か月ごろにはほとんどの子が2回になります。
午前に1回、午後早い時間に1回が目安です。だんだんと大人の生活リズムに近づいてきます。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★赤ちゃんが寝るときのベストな服装
赤ちゃんが寝つけない場合の原因は?
赤ちゃんがスムーズに寝てくれないと、ママやパパも睡眠不足になったり、ストレスを感じてしまうこともあるかもしれません。
赤ちゃんがなかなか寝つけないときの原因には、どのようなことがあるのでしょうか。
①お腹が空いている
赤ちゃんはお腹が空いていると、なかなか寝つくことができません。
特に新生児のころは一度に飲める母乳やミルクの量も少ないので、すぐにお腹が空いてしまいがちです。
なかなか寝てくれないときには授乳をして様子をみるとよいでしょう。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★新生児の授乳回数・間隔は?
②おむつが汚れている
赤ちゃんがなかなか寝つけないときは、おむつが汚れていないか確認しましょう。
赤ちゃんの肌は敏感なため、おむつが汚れているとかぶれたり、機嫌が悪くなったりすることがあります。
特に授乳後は排泄しやすいタイミングなので、こまめにチェックしましょう。
③部屋の温度が適切でない
授乳をしておむつを替えても寝つけないようであれば、部屋の温度が適切かどうかを確認しましょう。
赤ちゃんは大人に比べて体温調節機能が未熟なため、室温の影響を受けやすくなります。
部屋が暑すぎたり、寒すぎたりしていないか確認して室温を調節してください。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★新生児が快適な室温と湿度は?
④部屋が明るい
部屋が明るすぎると、赤ちゃんはうまく入眠できないことがあります。
寝かしつけをするときはカーテンを閉めたり、部屋の明かりを暗くしたりするなど、眠りやすくなるよう配慮をしましょう。
⑤便秘になっている
ウンチが出ず便秘になっていると、お腹が張るなどの不快感から寝つきにくくなります。
赤ちゃんの便秘に気がついたら、悪化する前に早めに受診をするとよいでしょう。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★赤ちゃんの便秘予防&解消法
⑥まだ眠くない
新生児のころは昼夜逆転していることも多く、夜になっても眠くならないことがあります。
赤ちゃんが寝ているときはママも一緒に睡眠をとるなど休むようにしましょう。
お昼寝と夜の睡眠の区別がつくようになってくるのは生後2か月ごろからです。
朝にはカーテンを開けて日光を浴び、夕方からは部屋を薄暗くするなどして、夜に眠たくなるよう体内時計を整えていくことが大切です。
⑦眠くなりすぎて興奮してしまった
赤ちゃんは眠くなりすぎると、興奮してなかなか寝つけないことがあります。
眠りたいという欲求が満たされず、その不快感が爆発し泣いてしまう。
これを一般的に「寝ぐずり」といいます。眠くなりすぎる前に寝かしつけをして睡眠に誘導する、睡眠が足りない場合はお昼寝の回数を増やすなどして対応しましょう。
⑧寝るための心の準備ができていない
楽しく遊んだ後、寝る前にリラックスモードへ切り替えていかないと、興奮してしまってなかなか寝つけない赤ちゃんもいます。
寝る前にはリラックスできる活動を取り入れたルーティーンを行うと、スムーズな入眠につながります。
寝る前のルーティーンは、ママやパパの負担にならないことも重要です。
「絵本を読む」「部屋を暗くする」など、親子ともにリラックスできる習慣を作れるとよいですね。
⑨特定の寝かしつけをしないと眠れない習慣がついている
抱っこをしないと寝ない、授乳をしてからでないと眠れないなど、特定の寝かしつけをしないと眠れない習慣がついている赤ちゃんもいます。
そうなると、寝たと思って布団におろした際に、睡眠が浅くなってまた泣いてしまうことがあります。
これを防ぐには、寝ついた後も睡眠が深くなるまでしばらく待ってから布団におろすか、最初から布団に横になって眠る習慣をつけていくとよいでしょう。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★【保育士監修】寝かしつけをスムーズにする方法とコツ
ベビーベッドとベビー布団、どちらで寝かせる?
赤ちゃんを寝かせるのに、ベビーベッドとベビー布団どちらがよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットを紹介するので、ぜひ判断の参考にしてみてくださいね。
ベビーベッドのメリット・デメリット
ベビーベッドには、次のようなメリットがあります。
<メリット>
- 立ったまま赤ちゃんのお世話ができるのでラク
(特に帝王切開による出産の場合、退院後もしばらくは傷が痛むため、立ったままお世話ができるのはラクという意見も) - 赤ちゃんにとって安全な環境を作りやすい
- 床から高さがあるため、ほこりや湿気の影響を受けにくい
- ベッド下のスペースを収納として活用できる (おむつのストックなど赤ちゃんのお世話グッズを収納すると、すぐに取り出せて便利)
- 兄姉やペットがいる場合、赤ちゃんが踏まれる心配がない
一方で、次のようなデメリットもあります。
<デメリット>
- 使用期間が短いこともある
- 使用しなくなったあと場所をとる
- 赤ちゃんが動けるようになると、転落や柵に頭をぶつけるなどの心配がある
- 添い寝がしにくい
- 授乳やおむつ替えなど、お世話のたびに柵を上げ下げするのが面倒
使用期間が短くなる可能性や、使用後は場所をとることなどデメリットを踏まえると、レンタルするという選択肢も視野にいれるとよいかもしれませんね。
【こちらの記事も確認してみましょう♪】
★ベビーベッドはどんな家庭に向いている?
ベビー布団のメリット・デメリット
ベビー布団には、次のようなメリットがあります。
<メリット>
- 添い寝がしやすい(ママの布団の隣に敷けば夜間授乳がラク)
- 柵がないのでお世話がしやすい
- 部屋の間取りに左右されず場所を確保しやすい
- 落下や柵にぶつかるなどの心配がない
- 部屋に圧迫感がない
一方で次のようなデメリットもあります。
<デメリット>
- 赤ちゃんが動けるようになると、寝室全体から危険なものを取り除く必要がある
- 床のほこりを赤ちゃんが吸い込みやすい
- 布団に湿気がたまりやすい
- ママやパパの足音や振動が伝わりやすい
- 兄姉やペットがいる場合、赤ちゃんが踏まれてしまう危険がある
夜泣きを防ぐための対策
赤ちゃんの夜泣きが続くと、ママやパパも眠れず困ってしまいますよね。夜泣きを少なくし、赤ちゃんが朝までぐっすり寝やすくなるヒントをご紹介します。
規則正しい生活リズムを整える
生まれたばかりの赤ちゃんは頻繁に寝たり起きたりを繰り返しますが、生後2~4か月くらいになると昼夜の区別が大分はっきりしてきます。
そのころには毎日決まった時間に起き、お出かけをしたり、お風呂などを済ませて布団に入るなど、規則正しい生活リズムを意識することが大切です。
決まった生活リズムを繰り返すことで、次第に赤ちゃんの体内時計も整っていくでしょう。
授乳のタイミングを調整する
夜間授乳が習慣化していると、赤ちゃんは夜中に目を覚ましやすくなります。
そのため赤ちゃんが寝る前にしっかり授乳を済ませておくなど、なるべく夜に目を覚まさないようタイミングを調整することもひとつの方法です。
また、お腹が空いていないタイミングで寝かしつけをするときは、授乳以外の方法で寝かせられるように少しずつ練習していくとよいでしょう。
【こちらの記事も確認しておきましょう♪】
★夜間授乳はいつまで必要?夜間の回数を減らしていく方法
夜泣き対策グッズを使う
生後2~4か月ごろは特に、抱っこをしても授乳をしてもなかなか寝ついてくれないということもあります。
そんなときは、夜泣き対策グッズを試してみてもよいでしょう。
夜泣きグッズにはメリーやホームシアター、おしゃぶりやラトル、絵本やバウンサーなどさまざまなものがありますが、わが子に合ったものを探してみてください。
【こちらの記事も要チェック】
★赤ちゃんの夜泣きの理由と効果的な対応
赤ちゃん自身のリズムに合わせましょう!
赤ちゃんの睡眠時間やリズムは十人十色。まとまって寝る子もいれば、短い時間ですぐに起きてしまう子もいます。
また、日によっても異なり、成長とともにどんどん変化していきます。
理想的な睡眠時間はあくまでも目安として捉えてください。
神経質になりすぎず、赤ちゃん自身のリズムに合わせて見守っていけたらよいですね。
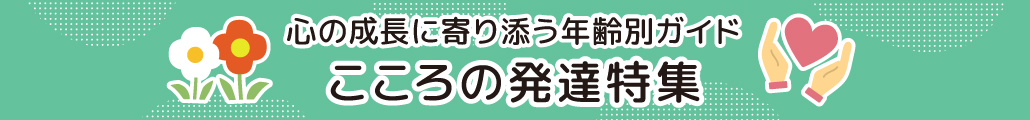

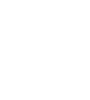























 キッズアライズを友だち追加
キッズアライズを友だち追加






 気になるキーワードで探す
気になるキーワードで探す 年齢×ジャンルで探す
年齢×ジャンルで探す